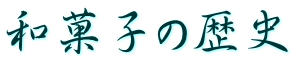
「和食」が世界遺産に登録されたのは、平成の終わりです。では、和菓子はいつ頃からあったのでしょうか。
日本人が「菓子」を食するようになったのは、どうやら私たちの知らない時代からのようです。年表にまとめてみました。
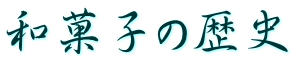
「和食」が世界遺産に登録されたのは、平成の終わりです。では、和菓子はいつ頃からあったのでしょうか。
日本人が「菓子」を食するようになったのは、どうやら私たちの知らない時代からのようです。年表にまとめてみました。
| |
||
| 古代 | □人々は空腹を感じると「古能美」(木の実)や「久多毛能」(果物)を食べていました。 この間食を「果子」といいます。 ■食物を加工する技術がなかったため果物の甘みを特別なものとし、主食と区別していました。 □果物を乾燥させたり木の実を砕いて灰汁を抜き団子にしていました。 |
 「ホームページ・ビルダークラシック」より引用 |
| 奈良 | □遣唐使が唐から「唐菓子」(からくだもの・からがし)を持ち帰りましたた。 ・梅枝(ばいし) ・桃子(とうし) ・餲餬(かっこ) ・桂心(けいしん) ・黏臍(てんせい) ・饆饠(ひちら) ・鎚子(ついし) ・団喜(だんき) ■唐菓子は祭祀の時のお供え物や献上品として用いられました。 □ 砂糖が伝わりました。砂糖は貴重だったため上流階級の一部の人だけが口にできました。 |
|
| 鎌倉 | ■茶道 栄西(ようさい)禅師が大陸から持ち帰りました。 | |
| 室町 | □「羊羹」誕生! 誕生当時は「蒸羊羹」でしたが、寒天が発見され「煉羊羹」が誕生しました。 | |
| 安土桃山 | ■ポルトガルやスペインから「南蛮菓子」が伝わりました。 □南蛮菓子は現在食べられている和菓子の原型です。 カステイラ(カステラ)・ビスカウト(ビスケット)・ボーロ等 |
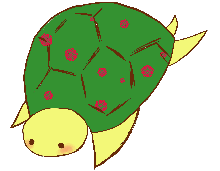 メンバーが作成 |
| 江戸 | ■国内での戦が止んだことで菓子作りに力を入れられるようになり、飛躍的に発展しました。 □城下町や門前町で独特の和菓子が誕生しました。 ■京菓子(京都)と上菓子(江戸)が競い合うように菓子の名前や見た目に工夫を凝らすようになりました。 □上流階級だけでなく庶民も菓子を楽しめるようになりました。(大福・桜餅・かりんとう等) |
 「ホームページ・ビルダークラシック」より引用 |
| |
||
| 明治 | ■西洋の文化が伝わり和菓子に大きな影響を与えました。 □ヨーロッパの調理器具(オーブン等)が影響し、焼き菓子等が誕生しました。 |
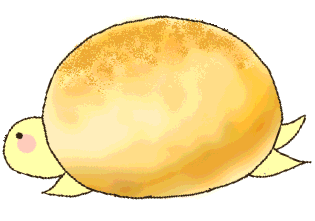 メンバーが作成 |
| |
||
| 昭和 | ■日中戦争~太平洋戦争の間は世間一般では菓子を味わうゆとりがありませんでした。 海軍や陸軍には羊羹が納められていました。 出征兵には落雁が贈られました。 □第二次世界大戦後の食料難で休廃業した菓子屋が多かったです。 ■経済成長で菓子の消費量が増え、クリームやバター等の素材を使った和菓子も作られるようになりました。 □クリスマス等の外来行事に合わせた和菓子も作られるようになり、サンタなど今までなかったモチーフも増えてきました。 |
 「ホームページ・ビルダークラシック」より引用 |
| |
||
| 平成 | ■平成25(2013)年 ユネスコの無形文化遺産に和食が登録されました! |  「素材庭園(ふりーイラスト素材集)~花・動物・食べ物・人物・雑貨他」より引用 |