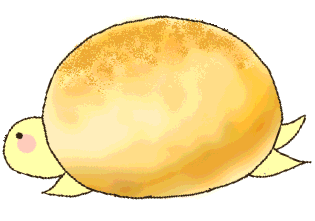| 私たちの地元の野中屋でいばらまんじゅうを作っているところを見学&お話を聞かせていただきました。 ここでは野中屋四代目店主の中西さんから教えていただいたことをQ&A形式で紹介します。 |
![]()
| 葉はサルトリイバラ(猿捕茨)を使っています。始まりは関東では一般的な柏の葉が手に入り難い関西で、いばらの葉を代用した事が始まりとのことです。中部地方も柏の葉が入手し難かったようで、昔は専ら「いばら餅」でした。またこの葉をサンキラ葉と言うらしく、「いばら餅」をサンキラ餅とも呼びます。サンキラ、正確にはサンライと言い、山帰来と書きます。サルトルイバラの別称だそうです。山帰来の名前は、『昔は毒消しの実として使われていたそうで、山野に多く自生ているため栽培をおこなうことはせず、毒消しの必要がある時に山に入り実を食べて帰ってくるという利用をされていたこと』が由来になっているそうです。 |
★いばらまんじゅうについて ★玉城最中について ★和菓子の良いところ
和菓子のいばらまんじゅうにはどのような材料が使われているのですか? |
基本的には、あん1:皮1の割合で、それを茨(いばら)の葉の間に挟んで作ります。 ・あん:北海道産小豆 ・生地(皮):砂糖 小麦粉 塩 などが原料です。 ・葉:中国産. |
||
| 生地 | あんこ | 茨の葉 | |
| 茨(いばら)の葉は、昔は地元の勝田地区の山で採れました。今は中国から輸入しています。いばらまんじゅうをつつむ葉にもサイズがあり、まんじゅうにあった葉っぱを注文するそうです。今年は「(5月上旬GW~6月)が山が荒れてあまり採れなくなったそうです。 皮は、口溶けを大事にするために中力粉をつかって堅すぎずやわらかすぎずに※グルテンを調節してほどよい堅さにしています。 あんこも口溶けをなめらかにするためにうらごしのあみの目をこまかくして敏感な舌でもなめらかさを感じるようにつくられています。 皮と餡を1:2のわりあいで作ることを3つ種といいます。 野中屋では3つ種をいばらまんじゅうに採用していました。野中屋では北海道産のあんこを使用しているのですが、小豆を作っていた日本の農家さんが、自然災害を受けた際の補償割合が高い大豆をつくり始めることが多くなったため、補償割合が低い小豆も日本で仕入れることが難しくなってきています。 野中屋のように原材料を巡る問題が今の日本に起こっています。 あんにつかう小豆、饅頭を包む葉っぱ、皮のお米などの原材料は、カナダ・アメリカ・中国などの外国産を仕入れるようになっています。特に今年は(2019年7月29日現在)北海道産の小豆が台風によって値段が上がり、出回る量も少なくなっているのでさらに外国産にたよるようになってきています。これは和菓子だけの問題だけでなく日本の輸入依存率にも関わってきます。(とは言っても最近は中国産の質もよくなって来ているそうです。) |
|||
| |
|||
![]()
| ※グルテンとは? 小麦や大麦に含まれるたんぱく質の一種です。 小麦粉に水をくわえてこねることでもちもちとした食感をだします。 それは水によって性質が異なるたんぱく質「グリアジン」と「グルテニン」がくっついて「グルテン」になる仕組みです。 |
★いばらまんじゅう豆知識 ・茨饅頭は田植えの時のお菓子でそのときによく食べられるそうです。 ・野中屋のいばらまんじゅうは1個12匁 (1匁 mom 3.75g) です。 13匁の時もあったけど増税によって値上げするより小さくしたそうです。 |
野中屋で一番人気の玉城最中について教えてください。 |
野中屋では玉城最中が大黒柱というほど一番売れてます。 我が町出身で有名な村山龍平が 「玉城最中や永寿楽 あぶれば風味 ことに香ばし」という言葉を残したほどおいしいと有名だそうです。 この言葉はしけってきた最中をあぶると皮がかりかりになり香ばしいという意味です。 ※ 永寿楽:(えいじゅらく)とは朝顔の一種 玉城最中は、昭和20年頃、もともとは「玉城錦」というお菓子で皮に羊羹を流していました。しかし、もっと皮の香りを引き立たせるため羊羹からあんこにしたという歴史があります。こうしてとどんな季節でも楽しめるお菓子になりました。 |
 |
|
| 和菓子の良いところ、和菓子に触れて良かったことを教えてください。 |
ここ野中屋の職人さんはお客さんが喜んでお菓子を食べてくれるところが和菓子職人いちばんの醍醐味です。 和菓子はいろいろなところで登場したり、たいていの物は作れたりしておもしろいです。また、和菓子は季節に関係する物が多いため、和菓子を作ることによって季節を感じることができるのが魅力です。 |
 |
|