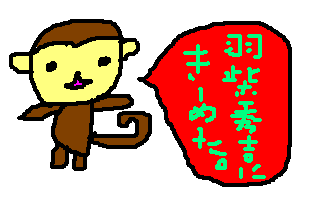
藤吉郎と光秀が徒武者の先頭に馬をならべて伊勢へとむかいつつ、
「いやぁ、明智殿。かの斎藤道三が生きておわした頃、そなたのことを
、秀才、天才、鬼才、偉才がっさいと、ほめちぎっておられたぞ。」
道三などには合ったこともないのに、藤吉郎、しゃあしゃあとほざいている。
(斎藤道三は濃姫の父。その濃姫のいとこなら、道三が光秀をほめちぎってもよかろうじゃないか。ハハハ、ひふへほ。)
「これは・・・・・・お世辞にしても、嬉しいことを。」
光秀が、まんざらでもない。
「わしはお世辞は大嫌いじゃ。お主のように実力のある人間にこびるのが一番みにくい。」
などと言うから、光秀はますます気を良くしている。
「そうだ。わしは伊勢から戻ったら、明智殿の秀の一字をちょうだいして、秀吉と名を改めることにしよう。
そなたの才能にあやかりたいからのう。」
「そう持ち上げられては、馬から落ちて落馬しまする。ハハハ。」
「ついでにこの際、苗字もかえよう。木の下では陽も当たらぬわい。羽柴にしよう。」
「はしば?どのような字でござるか?」
「丹羽長秀殿の、羽。柴田勝家殿の、柴。そして明智光秀殿の、秀じゃ。
これだけの人物にあやかれば、ひょっとしてわしが天下を取れるかもしれぬ。
うん、いずれは羽柴秀吉と名乗ろう。きーめた。」
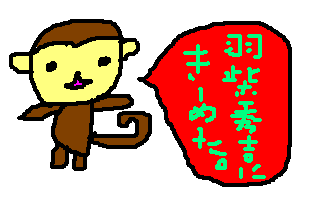
「おお、ご両人。待ちかねておったぞ。」
滝川一益が喜んでむかえた。