(2005�N 6��13�� (Mon) 09:14) (2002�N10�� 8�� (Tue) 11:30)
(2002�N 8��18�� (Sun) 13:13) (2002�N 8��16�� (Fri) 09:46)
(2001�N10��18�� (Thu) 12:10)
![]() �䕗�́A�ǂ̂悤�Ȃ����݂Ŕ�������̂ł����H
�䕗�́A�ǂ̂悤�Ȃ����݂Ŕ�������̂ł����H
![]() �䕗�̑傫���́A�ǂ̂悤�ɂ͂���̂ł����H
�䕗�̑傫���́A�ǂ̂悤�ɂ͂���̂ł����H
(2005�N 6��13�� (Mon) 09:14) (2002�N10�� 8�� (Tue) 11:30)
(2002�N 8��18�� (Sun) 13:13) (2002�N 8��16�� (Fri) 09:46)
(2001�N10��18�� (Thu) 12:10)
�䕗�́A�ԓ��t�߂Ŕ���������C�������B�������̂ł��B���̂��߁A�ł����́u�M�ђ�C���v�Ɠ����ł��B
�䕗�Ƃ������O���t���Ă��܂����A���́A�䕗�͂����̑傫�Ȓ�C���ł��B�������A��C���ɂ͂Q�̎�ނ������āA�䕗�͂��̕Е��̒�C���̑�^�̂��̂ł��B�Q�̎�ނŔ����̎d�����قȂ�܂��̂ňȉ��ɐ������܂��B
�ӂ��̒�C���́A���{�̋߂��̋�̍����Ƃ���𐁂��ΐ����Ƃ��������w�r�̂悤�ɃN�l�N�l�Ȃ��邱�ƂŔ������鏬���ȉQ���������Ŕ������܂��B���̓��{�t��(���ܓx)�Ŕ���������C���̂��Ƃ�"���ђ�C��"�Ƃ����܂��B�ӂ��A��C���ƌ����Ƃ��͂��̉��ђ�C���̂��Ƃ��w���܂��B
������́A�ԓ��t�߂̉������C��������������c��ȗʂ̐����C�����Ŕ������܂��B���̒�C����"�M�ђ�C��"�ƌĂ�ł��܂��B���̔M�ђ�C���̒��łƂĂ��傫�Ȃ��́i��C���̒��S�t�߂̕�����17.2m�ȏ�j��"�䕗"�ƌĂ�ł��܂��B�䕗�͉����ԓ��߂��̊C�̏�Ŕ������ē��{�܂ł͂�闷�����Ă���ė��܂��B
�䕗�̑傫���́A������i����15m/s�ȏ�̗̈�j�̔��a�ɂ���ĊK���ɕ����Ă��܂��B�䕗�̑傫���⋭�����ǂ̂悤�ɐ������Ă��邩���Ă݂�̂��ʔ����ł��ˁB���̋����́A�e�n�̊ϑ�����C�m�C�ۊϑ��D�A�C�m�C�ۃu�C�ȂǂŊϑ����Ă��܂��B
�䕗�ɂ��āA�ڂ������䕗�@STEP�P�����Q�Ƃ��������B�i���E���j
![]() ���{�ւ���Ă���䕗�͂ǂ̂悤�Ȍo�H��ʂ�̂ł����H
���{�ւ���Ă���䕗�͂ǂ̂悤�Ȍo�H��ʂ�̂ł����H
(2003�N 9��29�� (Mon) 09:53)
(2002�N 9�� 5�� (Thu) 11:22)
(2002�N 9�� 1�� (Sun) 16:46)
(2002�N 8��11�� (Sun) 10:35)
��{�I�ɑ䕗�͐ԓ��̏����k�Ő��܂�A�䕗���g�̐����ɂ��k�サ�܂����i����͖k�ɍs���s���قǃR���I���͂��傫���Ȃ邽�߂ł��B�j�A�f�Օ���ΐ����ɗ�����܂��B
�܂��A��ܓx�тł́A�k���f�Օ��ɗ�����Đ����ɖk�サ�܂��B�����ē��{���܂ޒ��ܓx�тɂ���ƕΐ����ɗ�����k���Ɉړ����܂��B�������A�����m���C�����o�H���ӂ���
�ł����肷��ƁA���̂ւ��`���Ĉړ����܂��B�i���A���j<2006/03/13�X�V>
![]() �Ȃ��䕗�͏H����Ăɂł��邩�����Ă��������B
�Ȃ��䕗�͏H����Ăɂł��邩�����Ă��������B
(2005�N10��18�� (Tue) 10:57)
(2004�N 7��12�� (Mon) 19:01)
(2002�N11�� 4�� (Mon) 12:28) (2002�N 9�� 7�� (Sat) 15:05)
(2001�N10��18�� (Thu) 14:31)
�䕗�͍����̐����C��K�v�Ƃ���̂ŁA�~�̔������͏��Ȃ��Ȃ�܂��B�������A�Ă���H�ȊO�ɁA�t�ɂ��������Ă��܂��B�����A�M�ѐ��܂�̑䕗�����{�܂ł���Ă��邩�ǂ����́A�ΐ����Ȃǂ̏��̕��⑾���m���C���̈ʒu�E�����Ȃǂɉe�������̂ŁA���{�ɂ͉Ă���H�ɂ����đ�������Ă���̂ł��B
�Ă̍Ő����́A�����m���C���ɓ��{��������̂ő䕗�͓��{�����邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�܂��B�i���A���j<2006/03/13�X�V>
![]() �~�̋C���z�u��"��������"�Ȃ̂ɁA�ǂ����đ����m���͐����̂ł����H
(2004�N 9��27�� (Mon) 10:45)
�~�̋C���z�u��"��������"�Ȃ̂ɁA�ǂ����đ����m���͐����̂ł����H
(2004�N 9��27�� (Mon) 10:45)
�m���ɓ~�̑�\�I�ȋC���z�u��ސ�������"�ł��B�������A�����ł�����C���͓��{�𒆐S�ɂ������V�C�}�œ����ɂ�����̂ŁA���{�̏�ɂ����邱�Ƃ͂��܂肠��܂���B���̂��߁A���̒�C���ɂ���ē��{�ʼnJ���~�����肷�邱�Ƃ͏��Ȃ��ł��B
�����m���������̂́A���{�C���̐�Ƒ傫�ȊW������܂��B�₽����C�������������ɂ��鍂�C�����琁���o�������́A���{�C���ł����ς�����~�点�Đ����������Ă��܂��̂ŁA�����m���ɂ��邱��ɂ͉_�����قǐ����������Ă��܂���B���̂��߁A�����m���ł͐����̂ł��B�i���j<2004/09/28�X�V>
�@
![]() ���ł�������������C���A���C���Ƃ����̂ł����H
���ł�������������C���A���C���Ƃ����̂ł����H
(2002�N11��28�� (Thu) 18:41)
��C���⍂�C���̊�͂��̎���̒n��̋C���Ɂh��ׂāh�Ⴂ���������ł��B�ǂ�hPa���炪��C���A���C���Ƃ�����͂���܂���B�i���j<2002/11/29�X�V>
�@
![]() ���C���ƒ�C���̋��ڂ��Ăǂ��ł����H
���C���ƒ�C���̋��ڂ��Ăǂ��ł����H
(2003�N 8��27�� (Wed) 10:10)
���C���͎���ɔ�ׂċC���̍����Ƃ���A��C���͋C���̒Ⴂ�Ƃ���ł�����A���̊Ԃ͂����Č����u���ʂ̋C���̂Ƃ���v�ł��B�i���j<2003/08/30�X�V>
�@
![]() ��C���̂Ƃ���͂Ȃ��V�C�������̂ł����H
��C���̂Ƃ���͂Ȃ��V�C�������̂ł����H
(2002�N 8�� 8�� (Thu) 21:05)
��C���̂���Ƃ���ɂ͏㏸�C�����N���܂��B�㏸�C���ɂ���ĉ_���ł��J���~��܂�����A��C���̂���Ƃ���͓V�C�������Ȃ�܂��B
�ڂ������_�̂��Ɓ@STEP�P���������������B�i���j<2002/08/12�X�V>
![]() ���{�߂��Œ�C�����O�����Ƃ��ɂ́A�Ȃ����g�O���������Ŋ���O���������ɂł���̂ł����H�����āA���̊���O���̕����ړ����x�������̂͂Ȃ��ł����H
���{�߂��Œ�C�����O�����Ƃ��ɂ́A�Ȃ����g�O���������Ŋ���O���������ɂł���̂ł����H�����āA���̊���O���̕����ړ����x�������̂͂Ȃ��ł����H
(2004�N 2�� 8�� (Sun) 21:25)
(2002�N 8�� 1�� (Thu) 14:07)
��C���ɂ́A���S�Ɍ������Ĕ����v���i�����j�ɕ�����������ł��܂��B���̂��߁A�����ł͓�̒g������C�����ꍞ��Ŋ���O�����A�����ɂ͖k�̗₽����C�����ꍞ��ʼn��g�O�����ł��܂��B
����O����艷�g�O���̂ق����������x���̂́A���g�O���̏ꍇ�A�₽����C�̏�ɒg������C�����グ�Ă����̂ŁA���ڗ₽����C�������͂��ア����ł��B�i���A���j<2004/02/09�X�V>
�@
![]() �C�����ĂȂ�ł����H�[���C�̒�ɐ���ƋC���͂ǂ��Ȃ�܂����H
�C�����ĂȂ�ł����H�[���C�̒�ɐ���ƋC���͂ǂ��Ȃ�܂����H
(2003�N 8��29�� (Fri) 23:02) (2003�N 8�� 3�� (Sun) 11:18)
(2003�N 2��14�� (Fri) 10:09) (2002�N 8��20�� (Tue) 11:06)
�C���Ƃ����̂́A��C�������������Ƃɂ���Đ��܂�鈳�͂̂��Ƃł��B�C���͕��̂������Ԃ��悤�ɂ�����������瓭���܂��B
�C���̑傫���͂��̈ʒu������ɂ����C�̗ʂɔ�Ⴕ�܂��B��C�͑�C���܂ł�������܂���A����ɏオ��Ƃ��̈ʒu������̑�C�����Ȃ��Ȃ邽�߁A�C����������܂��B
�[���C�̒�ɐ������ꍇ�ł����A�����ł͐������͂������Ă��܂��B����𐅈��Ƃ����܂��B
�C�ʂł̍����̋C����1�C���Ƃ����A����͐��[10���ł̐������������Ȃ�܂��B
�Ⴆ�A���[��1000���ł���ΐ�����100�C���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ń|�C���g�Ȃ̂́A�����ł��C���͂�����Ƃ������Ƃł��B
�܂�A���[1000m�ɂ��镨�̂��鈳�͂�1�C���Ɛ����ɂ��100�C���Ȃ̂�101�C���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
1�C����1013hPa����1kg�d/c�u�ł��B
hPa�̓w�N�g�p�X�J���Ƃ����A���ʁA��C����\�����ɂ͂��̒P�ʂ��g���܂��B
���̂��Ɓ@STEP1�����Ă݂Ă��������B�i�܁A���j<2006/03/12�X�V>
�@
![]() �C�ʂƓ��������̂Ƃ���ł̋C����1013hPa�ƏK���܂������A�Ȃ�1013hPa���C���������Ȃ邱�Ƃ�����̂ł����H
�C�ʂƓ��������̂Ƃ���ł̋C����1013hPa�ƏK���܂������A�Ȃ�1013hPa���C���������Ȃ邱�Ƃ�����̂ł����H
(2002�N11��14�� (Thu) 18:18)
�C�ʂƓ��������̂Ƃ���̋C���́A��{�I�ɂ�1013hPa�ł����A���ۂɂ͋C��������������Ⴉ�����肵�܂��B�C���̍��ނЂƂ̌����́A��C�̉��x�����łȂ����Ƃł��B
�C�̂̐����ɂ��A���x�������Ȃ�Ƌ�C�͂ӂ���݁A���x���Ⴍ�Ȃ�Ƌ�C�͂��ڂ݂܂��B��C���ӂ�������Ƃ���Ƃ��ɂ́A�L����Ԃ��K�v�ƂȂ�̂Ŏ���̑�C�������Ď����̋�Ԃ��m�ۂ��悤�Ƃ��܂��B���ꂪ��C�������߂錴���ƂȂ�܂��B
�V�C�}�ɂ́A�l�X�ȑ傫���̋C����������Ă��܂��B��C���A���C���̂����̂��A�C���ɍ������邱�Ƃ��炫�Ă��܂��B�V�C�}�ɏ�����Ă���Ⴂ�C�����A�W���̍������́A��C�̉��x���ȂǗl�X�ȋC�ۏ����������ƂȂ��Ă��܂��B�i���j<2002/11/16�X�V>
![]() �C���ƋC���̊W�́H
�C���ƋC���̊W�́H
(2002�N12��25�� (Wed) 16:32)
(2001�N11��10�� (Sat) 01:03)
�C���Ƒ̐ς͔����̊W������܂��B�Ⴆ�A��C�����k����Ƒ̐ς�����܂����A�t�ɉ����߂����Ƃ���͂����܂�܂��B���ꂪ�C���̍����Ȃ������ł��B�t�ɁA�n��ŋ�C���l�߂��y�b�g�{�g�����C���̒Ⴂ�W���̍����Ƃ���Ɏ����Ă����Ɩc��ނ��Ƃ�����킩��܂�
�i�y�b�g�{�g���̒��͒n��̋C���̂܂܂Ȃ̂ŁA���ΓI�ɋC���������Ȃ�܂��j�B
���āA�̐ς�������A�܂��C���c��ގ��ɂ́A��C���̂��G�l���M�[���g���܂��B��C�̎��G�l���M�[�́A���x�A�܂�M�G�l���M�[�ł��B�M�G�l���M�[���g���ƁA���x��������܂��B
�܂�܂Ƃ߂�ƁA�C����������Ƒ̐ς������A����ɂ���ĉ��x��������̂ł��B����͒f�M�ω��ƌĂ�Ă��܂��B�i���j<2006/03/06�X�V>
![]() hPa�͂ǂ̂悤�ȒP�ʂł����H
hPa�͂ǂ̂悤�ȒP�ʂł����H
(2005�N 7��13�� (Wed) 18:37)
(2002�N10��22�� (Tue) 20:17)
(2001�N 9��28�� (Fri) 11:35)
hPa�i�w�N�g�p�X�J���j�Ƃ����̂́A���͂�\���P�ʂł��B�Ȃ̂ŁA���l�͌��܂��Ă��܂��B�ڂ������Ƃ͍��Z�̗��ȁi�����j�ŏK���܂��B
h�i�w�N�g�j��100�{��\���L���ŁAhPa��Pa�i�p�X�J���j��100�{�̑傫���ł��BPa��1�������[�g���������1N�i�j���[�g���j�̗͂����������Ƃ��̈��͂̑傫���ł��BN�Ƃ����P�ʂ�
�A�ŋ߂̒��w�̋��ȏ��ɂ͏o�Ă��邩������܂���B1N�͂�������0.1kg�d�i0.1kg�̂��̂��x���Ă���Ƃ��Ɋ�����d���i�́j�̑傫���j���炢�̗͂̑傫���ł��B
���ł܂Ƃ߂�ƁA
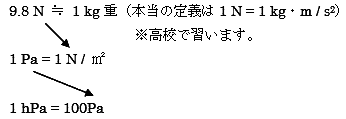
�̂悤�ɂȂ�܂��B�i���j<2006/03/06�X�V>
![]() �Ȃ��P�C����1013hPa�Ȃ̂ł����H
�Ȃ��P�C����1013hPa�Ȃ̂ł����H
(2004�N10��19�� (Tue) 08:58)
�C�ʂŎ�C�����P�C���ł��B�P�C���́u�P����cm�������Pkg�d�ŁA���⒌��760mm�����グ��傫���v�ƒ�`����Ă��܂��B
�p�X�J���́u�P�������[�g��������P�j���[�g���̈��͂̋����i�P�m�^�������[�g���j���P�p�X�J���v�ƒ�`����Ă��܂��B
�܂�P�C�����p�X�J���ŕ\���Ɩ�1013hpa�ł���A�Ƃ������Ƃł��B
���̒P�ʂŌ�����
�E�����@1���[�g����3.28�t�B�[�g
�E�M�ʁ@1�J�����[��4.2�W���[��
�ȂǂƓ��������ł��B�i�܁j<2004/10/19�X�V>
�@
![]() ��C���̎��ɓ����ɂ��Ȃ�����A�̂̒ɂ݂������Ȃ�̂͂Ȃ��ł����H
��C���̎��ɓ����ɂ��Ȃ�����A�̂̒ɂ݂������Ȃ�̂͂Ȃ��ł����H
(2005�N 6�� 8�� (Wed) 00:47) (2004�N 6��11�� (Fri) 00:16)
(2003�N 6��22�� (Sun) 12:10) (2001�N10�� 9�� (Tue) 21:58 )
�c�O�Ȃ���ڂ������Ƃ͂킩��܂��A�C���̕ω����g�̂ɉe����^���A�̂��K���ł����ɕs����i����Ƃ������Ƃ͂���悤�ł��B���̂悤�ɋC�ۂ��l�Ԃɗ^����e������������w����u���C�ۊw�v�Ƃ����܂��B�i���A�܁A���j<2006/03/13�X�V>
�@
![]() �Q�̑䕗���Ԃ�������ǂ��Ȃ�́H
�Q�̑䕗���Ԃ�������ǂ��Ȃ�́H
(2001�N10��31�� (Wed) 20:45)
�Q�̑䕗���߂Â��Ă��A�d�Ȃ����肹���ɂ��݂��ɔ����������A����Ă����܂��B
�Q�̑䕗���߂Â��ƁA�Q�̑䕗�̒��S����Ō���ŁA���̐������_�𒆐S�ɔ����v���ɉ�����悤�ɓ����܂��B�������Ă��邮�����Ėk�����ɗ����䕗�͓��{�̏�ɗ���鋭�������ɏ���Ėk���i�݁A����쐼���ɗ����䕗�͂��̂������������܂��B

���̓����́g�����̌��ʁh�ƌĂ�Ă��܂����A�Q�O�O�P�N�X���ɓ����{�≫��ɔ�Q�������炵���A�䕗�P�T���A�P�U���̂Q�̑䕗�����̗�ł��B�V���̓V�C�}��ǂ��Ă݂Ă͂������ł��傤���B�i���j<2001/11/02�X�V>
Copyright(C)2001-2006 ThinkQuest@Japan Team 40457 all rights reserved | Legal notice