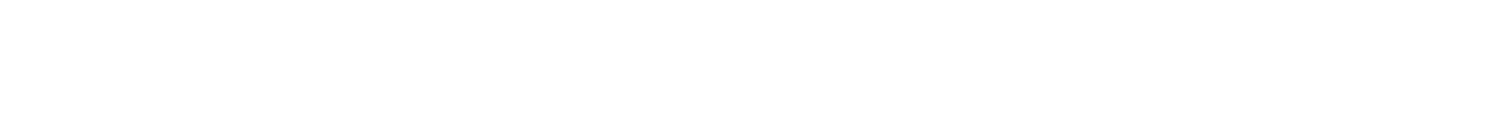社会情勢と制度の関わり
海外と日本の雇用形態の違い
コロナ禍とジョブ型雇用
現在の新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの企業で導入されたテレワークによって従来のような人的管理が難しくなり、その人の行った仕事について評価する必要が出てきました。 しかし飽くまでコロナ禍はひとつのきっかけに過ぎず、もともと同一労働同一賃金や賃金格差に踏み込み、働き方改革連法案の議題が出始めたのは2016年ごろなのです。 とはいえこのきっかけは労働者が体験しメリットを知ったことで大きなインパクトを与えました。 テレワークでは、上司は自宅で働く部下の仕事ぶりを把握しにくいというのが欠点です。しかしやるべき仕事内容を具体的に決めているジョブ型なら社員の仕事を可視化することが可能なのです。| 富士通 | 日立製作所 |
|---|---|
| オフィススペースを3年間で半減、 全社員を対象にジョブ型雇用へと移行 | 国内の16万人を含む全世界の従業員30万人をジョブ型雇用へ移行すると発表 |
実際に富士通が行った働き方改革
まとめ
・日本の雇用はチームでの仕事がメインであるため残業を発生させやすい
・海外の雇用は仕事が明確化されているので残業はほぼ発生しない
・コロナ禍によってテレワークが増え、ジョブ型雇用を採用する企業が増えつつある