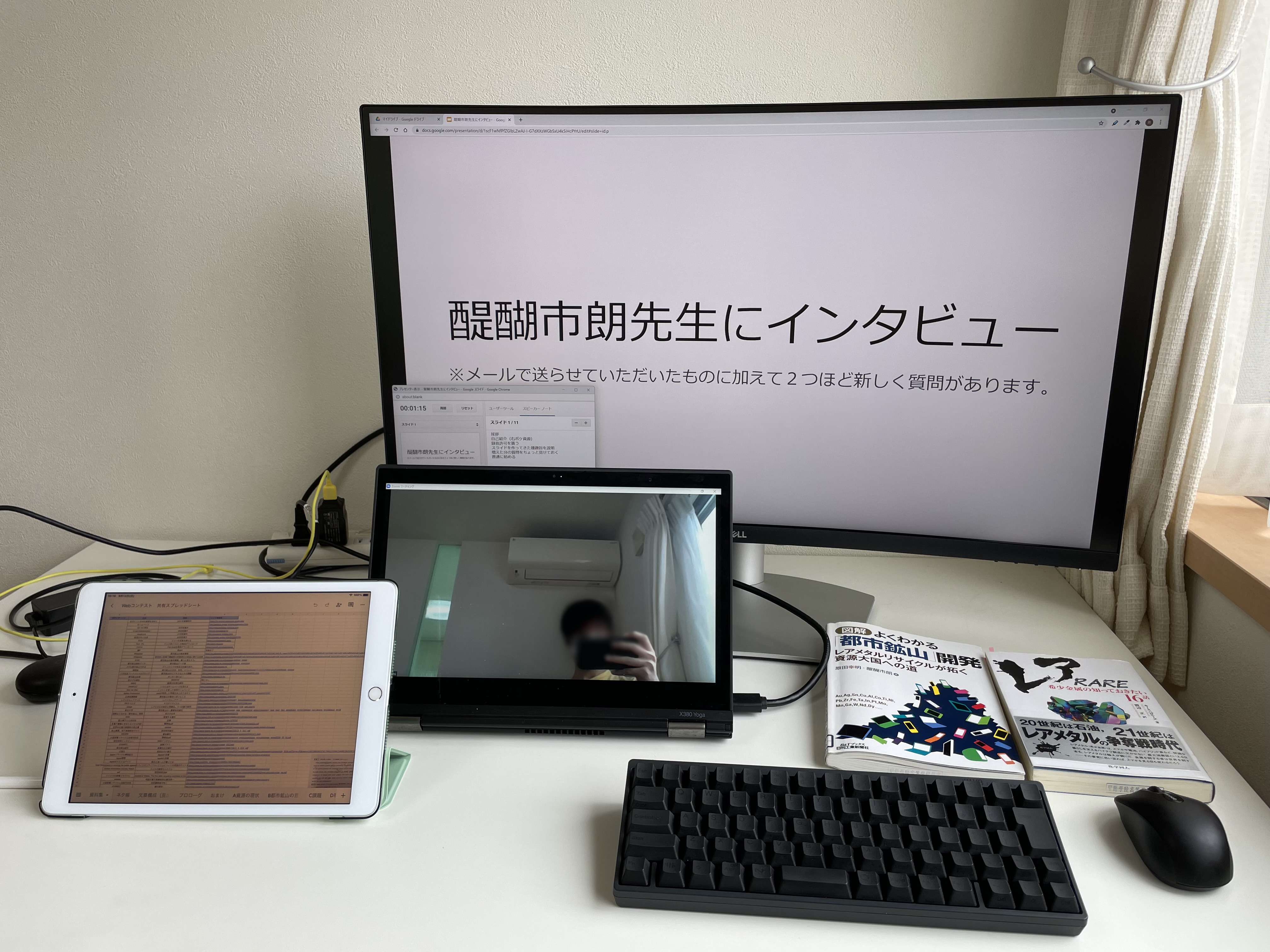インタビュー
2021年9月12日に東京大学先端科学技術研究センター准教授・醍醐市朗先生にZoomでお話を伺いました。
なおインタビューはGoogleスライドを使いながら行いました。 使用したGoogleスライドはこちらから閲覧できます。
プロフィール
醍醐市朗先生は2021年4月より東京大学先端科学技術研究センターの准教授を務められています。 材料の物質フロー・ストックについての研究をされており、都市鉱山に関する第一人者でもあります。
インタビュー
-
携帯電話が貴金属
貴金属
金 (Au)、銀 (Ag)、白金 (Pt)、パラジウム (Pd)、ロジウム
(Rh)、イリジウム (Ir)、ルテニウム (Ru)、オスミウム (Os)
、レニウム(Re)を総称して言う。
やレアメタル
レアメタル
1.地殻中の存在量が比較的少ない元素
2.単体として取り出すことが技術的に困難な元素
3.資源の産出国が偏在している
を満たす元素のことを言い、現代の産業に欠かせない”産業のビタミン”と呼ばれる。別名マイナーメタル。 を含んでいるといっても、銅まで合わせて全体の重量の約1割しかなく、残りの大部分はプラスチックなどの廃棄物になるそうなのですが、小型家電のリサイクルにおいてプラスチックは資源としてリサイクルすることはできないのでしょうか? - プラスチックをリサイクルするのは難しいと思います。 その大きな理由として、プラスチック単体のコストがプラスチックのリサイクルにかかるコストに見合っていないということが挙げられます。 携帯電話に含まれる金属類は基本的に銅の精錬 精錬 粗金属から不純物を取り除いて純度を上げること。 に入れれば全て回収できる一方で、プラスチックは単体分離するにどうしても人の手が必要になってきます。 しかし、そうして取り出されたプラスチックの価値は高いとは言えません。 そのため、銅精錬ではプラスチックは蒸し焼きにされ、炭化されることになっています。 以上のことから、プラスチックはリサイクルできないわけではありませんが、経済的な理由でリサイクルされていないという状況です。
- 日本において、大きな製品(自動車、冷蔵庫、テレビなど)のリサイクル率は高いのに対し、小さい製品(携帯電話など)はリサイクル率が低いのはなぜですか? 私たちは「家電リサイクル法 家電リサイクル法 エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目を対象とした法律。後払い制度がとられている。これらの家電の回収により、リサイクルの促進だけでなく、廃棄物の減量も目指している。 」と「小型家電リサイクル法 小型家電リサイクル法 日本で小型家電を対象として施工されているリサイクルに関する法律。家電リサイクル法などとは違い、法律に強制力はない。2021年8月10日に公布され、2013年4月1日から施工されている。 」の施行年数と強制力の強さの違いが関係していると思っているのですがどうでしょうか。
- それも理由の一つだと思います。 大型家電そして自動車に関しては「家電リサイクル法」、「自動車リサイクル法 自動車リサイクル法 車を対象とした法律。購入時にリサイクル代金を支払いリサイクル券を発行する前払い制度が取られている。2002年7月12日に公布され、2005年1月1日から施行されている。 」があるので、その法に則って処理しなければなりません。 特に「家電リサイクル法」は「小型家電リサイクル法」に比べて歴史も古く、リサイクルすることが義務付けられています。 その一方で、「小型家電リサイクル法」ではリサイクルが強制されていません。 この違いは、金属リサイクルの促進にあたっての2つの流れの差から生まれたものです。 1つは、リサイクルを強制することで、単一ルートで集中的に回収を進めるということであり、もう1つは、リサイクルの自由度を上げることで、幅広く効率的にリサイクルを行うということです。 家電リサイクル法が施行されるようになった背景には、昔から不法投棄や不法処理が目立っていたということがあります。 これらの不法投棄・不法処理を抑え、適正処理を推進するために大型製品には強制力の強い措置が適用されました。 一方で、携帯電話などの小型製品においては、リサイクルの自由度を優先し、「みんなのメダルプロジェクト みんなのメダルプロジェクト 東京2020オリンピック・パラリンピックにおける金・銀・銅メダルを都市鉱山から作るというプロジェクト。このプロジェクトによって約5000個のメダルが都市鉱山から作られた。 」をはじめとして幅広くリサイクルが行われています。 そのため、リサイクル率にリサイクル法の施行年数と強制力の差は関係していると言えます。 ただ、携帯電話に関してはまだいくつか要因があります。 というのは、目覚まし機能や写真の保存などの理由で使い終わった携帯電話を残しているということが多くあるということです。 そこは携帯電話の特殊性なのではないでしょうか。 また、小型家電は自動車や冷蔵庫に比べて家の中に残していても邪魔にならないということもリサイクル率が低いことの一因としてあると思います。
- 日本において消費者や企業にリサイクルを義務付ける法律を作ることはできないのでしょうか?
- 義務付けることはできますが、難しいと思います。 リサイクルを義務付けなければならないということは、コストメリットがないこととも言えます。 なぜなら、利益の出るものは義務付けなくても誰もがするからです。 つまり義務付けるというムチと一緒にアメも用意しなくてはならないのです。 では一体誰がそのアメ、つまりお金を負担するのでしょうか? それが国の予算から支出できればいいのですが、支出するにしても本当にそれがかかっている費用の元に提供できるかはわかりません。 かかっている費用以上に請求されて払っていたとすると国は損する一方です。 そのため、そのような部分の制度設計というのが簡単ではないように思います。
- 東京オリンピック・パラリンピック2020では「みんなのメダルプロジェクト」が無事成功に終わりましたが、その成功の理由とは何なのでしょうか?
- 「みんなのメダルプロジェクト」には、単にリサイクルを呼びかける場合と比べて大きな利点があります。 それは、使用済み携帯電話をリサイクルに出す人が、その携帯電話がオリンピック選手のメダルになることをはっきりと知っていたということです。 一方で、従来のリサイクルでは、回収ボックスに入れたものがリサイクルされることは知っていても、何にリサイクルされるかまではわかりません。 その点が、「みんなのメダルプロジェクト」が成功した理由のように思います。
- 金属リサイクルにおける日本の特徴について教えていただきたいです。
- 日本では、銅・鉛・亜鉛・鉄精錬を行うことができます。 このようにたくさんの種類の精錬を行うことができる国は多くありません。 そのうち銅・鉛・亜鉛精錬はそれぞれの精錬で出てきた飛灰などを含む残渣(ざんさ)から有価金属を回収するという関係にあります。 これを行うことによって、製品に含まれるほぼ全ての有価金属を回収することができますし、例えば銅精錬しかできない国では有害物質として管理しなければならない物質も、日本では有価金属として回収することができます。 これが金属リサイクルにおける日本の大きなアドバンテージとなっています。
- 都市鉱山が地球温暖化などと比べてあまり話題にならないのはなぜですか?
- 都市鉱山という言葉が初めて出たのは1980年代ですが、実際に使われるようになったのは2008年頃で、使われ始めて十数年しか経っていないということが大きな要因としてあると思います。 また、都市鉱山やリサイクルと聞くとなにかキレイでいいことをしているようなイメージがあるような気がしますが、実際は廃棄物処理の一部でしかないという面もあります。 今となっては違いますが、昔は廃棄物処理は階級の低い人によって行われていました。 その点では、廃棄物処理は社会の表舞台からは隠された部分の活動であったとも言えます。 現在は、リサイクルの進化によって廃棄物処理とリサイクルが繋がってきていますが、まだまだ金属を製品から一次資源 一次資源 まだ地中から掘り出されていない地下資源。 に戻す工程と二次資源 二次資源 地中から既に掘り出された地上資源。 を活用する工程が組み合っていないように感じます。 さらに、地球温暖化はエネルギーの消費によるCO2の発生で起きているため、意識的に省エネルギーに切り替えることで防ぐことができますが、資源枯渇の場合、意識的に防ぐことはできません。 例えば、パソコンを買うときに、資源節約のために金や銀があまり使われていないパソコンが欲しいと思っても選べませんよね。 そのため、資源枯渇ないし都市鉱山は、地球温暖化と比べて身近に感じにくいのだと思います。
- 資源枯渇について、耐用年数 耐用年数 資源が枯渇するまでの年数。埋蔵量を生産量で割った値。 が伸び続けているところもあり、「結局資源がなくならないのでは?」という考え方をする人もいると思うのですが、それについてどう思われますか?
- 例として銅の話を取り上げてみたいと思います。 昔は銅濃度が1.0%の鉱物が使われていましたが、今では銅濃度1.0%の鉱物は採り尽くされており、日本で出回っている鉱物のうち最も濃度が高いものでも0.6%となっています。 先日聞いた話によると、銅濃度0.3%の鉱物も使わなければいけなくなったというところもあるそうです。 このことから、資源が枯渇に近付いていそうだということを薄々感じているという人はいると思います。 また、枯渇は経済性が見合わなくなった結果採れなくなったという状況も指し、それは銅を含め、いくつかの元素が示しているので、10年前や20年前と比べると「結局資源はなくならない」と言う声はあまり聞かなくなったようにも感じます。
わかったことのまとめ
- リサイクル法は不法投棄・不法処理を抑えるために存在する
- 携帯電話の回収率は携帯電話特有の特徴が関係している
- 資源枯渇は着実に近づいてきている
なお、このサイトを作るにあたって、醍醐先生のお話を参考にさせていただいた箇所が多々あります。
貴重なお話ありがとうございました。
Interview
On September 12, 2021, we had a Zoom interview with Ichiro Daigo, associate professor at the Research Center for Advanced Science and Technology, University of Tokyo.
The interview was conducted using Google Slides. The Google slides can be viewed here.
Profile
Mr. Ichiro Daigo has been an Associate Professor at Research Center for Advanced Science and Technology, University of Tokyo since April 2021. His research focuses on the material flow and stock, and he is a leading expert on urban mining.
Interview
-
It is said that even though cell phones contain
precious metals
precious metals
Gold (Au), silver (Ag), platinum (Pt), palladium (Pd),
rhodium (Rh), iridium (Ir), ruthenium (Ru), osmium (Os),
and rhenium (Re).
and
minor metals
minor metals
Elements that satisfy the following conditions:
1. relatively low abundance in the earth's crust,
2. technically difficult to extract as a single element, and
3. unevenly distributed in resource-producing countries. , the total weight of the phone, including copper, is only about 10% of the total weight, and most of the rest is waste such as plastic. Is it possible to recycle such plastic as resources in the recycling of small home appliances? - I think it is difficult. One of the major reasons for this is that the cost of plastic alone is not worth the cost of recycling plastic. The metals contained in cell phones can be recovered by refining refining To remove impurities from crude metals in order to increase their purity. copper in them, while the plastics require human labor to separate them. However, the value of the plastic extracted in this way is not high. Therefore, in copper refining, plastics are steamed and carbonized. From the above, it is not that plastics cannot be recycled, but they are not being recycled for economic reasons.
- Why is the recycling rate of large products (cars, refrigerators, televisions, etc.) so high in Japan, while that of small products (cell phones, etc.) is so low? We suspect that the difference in the number of years “the Act on Recycling of Specified Kinds of Home Appliances the Act on Recycling of Specified Kinds of Home Appliances The law covering four home appliances: air conditioners, televisions (CRT, LCD, and plasma), refrigerators/freezers, and washing machines/clothes dryers. A deferred payment system has been adopted. By collecting these home appliances, it aims not only to promote recycling but also to reduce the amount of waste. ” and “the Act on Promotion of Recycling of Small Waste Electrical and Electronic Equipment the Act on Promotion of Recycling of Small Waste Electrical and Electronic Equipment A law on recycling of small home appliances in Japan. Unlike the Home Appliance Recycling Law and other laws, it is not that you have to follow it. It was promulgated on August 10, 2021 and became effective on April 1, 2013. ” have been in effect and the strength of their enforcement is related.
- I think that is one of the reasons. For large home appliances and automobiles, there is “the Act on Recycling of Specified Kinds of Home Appliances the Act on Recycling of Specified Kinds of Home Appliances The law covering four home appliances: air conditioners, televisions (CRT, LCD, and plasma), refrigerators/freezers, and washing machines/clothes dryers. A deferred payment system has been adopted. By collecting these home appliances, it aims not only to promote recycling but also to reduce the amount of waste. ” and the "Act on Recycling, etc, of End-of-Life Vehicles", and they must be disposed of in compliance with these laws. In particular, "Act on Recycling of Specified Kinds of Home Appliances" has a longer history than "Act on Promotion of Recycling of Small Waste Electrical and Electronic Equipment," and it forces us to recycle. On the other hand, recycling is not compulsory under the "Act on Promotion of Recycling of Small Waste Electrical and Electronic Equipment." This difference results from the difference between the two streams in promoting metal recycling. One is to enforce recycling and promote intensive collection through a single route, and the other is to increase the flexibility of recycling and make it efficient. One of the reasons why Act on Recycling of Specified Kinds of Home Appliances came into effect was that illegal disposal had been prominent in the past. In order to curb such illegal dumping and processing and to promote proper processing, compulsory measures have been applied to large products. On the contrary, for small products such as cell phones, the flexibility of recycling is prioritized and a wide range of recycling is being carried out, including the “Tokyo 2020 Medals Project Tokyo 2020 Medals Project A project to make gold, silver and bronze medals for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games from urban mines. Approximately 5,000 medals have been made from urban mines through this project. ”. Therefore, it can be said that the difference between the number of years the recycling law has been in effect and its enforcement is related to the recycling rate. There are still other reasons for cell phones. One of them is that many people keep their cell phones to use as alarm clocks or storage equipment. I think that is the uniqueness of cell phones, isn't it? I also think that one of the reasons for the low recycling rate is that small home appliances are less inconvenient to leave in their houses than cars and refrigerators.
- Is it possible to create a law in Japan that requires consumers and companies to recycle?
- It is possible, but very difficult. The fact that recycling must be compulsory also means that there is no benefit in terms of cost because everyone will do what is profitable, even if it is not a duty. In other words, we need to provide carrots along with the sticks of obligation. So who is going to pay for the carrots, that is the money? It would be nice if it could be paid from the national budget, but even if it is, we do not know if it can really be provided to where recycling cost is spent. If the government pays more than it is costing, they will continue to lose money. I do not think it is easy to design a system to resolve such problems.
- What are the reasons for the success of “Tokyo 2020 Medals Project" at the Tokyo Olympics and Paralympics 2020?
- Tokyo 2020 Medals Project has a big advantage over simply asking people to recycle. It is that people who serve their used cellphones for recycling knew that the phones would become medals for Olympic athletes. On the other hand, in conventional recycling, we know that what we put in the collection box will be recycled, but we do not know what it will be recycled into. I think that is why Tokyo 2020 Medals Project was so successful.
- What are the features of Japan in metal recycling?
- In Japan, copper, lead, zinc, and iron can be refined. Not many countries can provide such a large number of different types of refining. Of these, copper, lead and zinc refining collects valuable metals from residue including fly ash. By doing this, it is possible to collect almost all of the valuable metals in products, and for example in countries that can only refine copper substances that must be managed as hazardous substances can be recycled as valuable metals in Japan. This is a major advantage of Japan in metal recycling.
- Why is urban mining not discussed as much as global warming and other issues?
- The word "urban mines" was first used in the 1980s, but it only started to be actually used around 2008, which means that it has only been in use for more than a decade, and I think this is a major factor. Also, when you hear the words "urban mines" and "recycling," you may think that you are doing something beautiful and good, but in fact, it is only a part of waste disposal. It is different now, but in the past, waste management was done by lower class people. In this point of view, it can be said that waste management was an activity in a hidden part of society. Today, with the evolution of recycling, waste processing and recycling are becoming more and more connected, but I feel there is still a lot of work to be done in the process of returning metals from products to primary resources primary resources Resources that have not yet been dug out of the ground. and secondary resources secondary resources Resources that have already been dug out of the ground. . In addition, since global warming is caused by the generation of CO2 by energy consumption, it can be stopped by consciously switching to energy conservation, but in the case of resource starvation, it cannot be consciously prevented. For example, when you buy a computer, if you want a computer that uses less gold or silver to save resources, you cannot choose such one. For this reason, I think that resource depletion and urban mines are less familiar to us than global warming.
- Some people think that resources will not run out in the end because the service life service life The number of years until a resource runs out. The value calculated by dividing the amount of reserves by that of production. will continue to increase forever. What do you think about this idea?
- I would like to take up the story of copper as an example. In the past, minerals with a copper content of 1.0% were used, but now minerals with a copper content of 1.0% have been exhausted, and even the highest copper content mineral available in Japan is 0.6%. According to a recent story I heard, some places are now required to use minerals with a copper content of 0.3%. From this, I think some people feel vaguely that we are likely to be approaching resource depletion. Depletion also refers to a situation where the resource can no longer be mined because it is not cost-effective to do so, as some elements, including copper, are showing such situation, so we do not seem to hear as many people saying "the resource will not disappear after all" as we did 10 or 20 years ago.
What We Learned
- The recycling law exists to control illegal disposal and processing.
- The collection rate of cell phones is related to their unique characteristics.
- Resource exhaustion is steadily approaching.
Also, we used many of associate professor Daigo's stories as a guide in creating this site. Thank you for sharing your valuable story.