その他の権利
知的財産には、今まで学習してきた以外にもいくつかの権利が存在します。ここでは、その権利について学習していきます。
育成者権とは、新しく育てられた品種を保護するための権利です。 農林水産省が管轄しており、農林水産業の発展を実現する事を目的とした権利です。保護された品種は主に種苗、収穫物、加工品の販売―を独占できます。

区別性
従来ある商品と区別できるか。
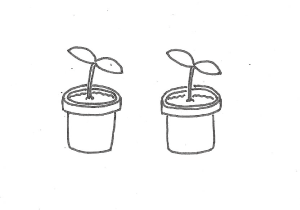
安定性
同じ植物が安定的に繁殖できるか。

未譲渡性
最初の販売から1年以内。外国においては4年以内に他人に出願品種を渡していないこと。
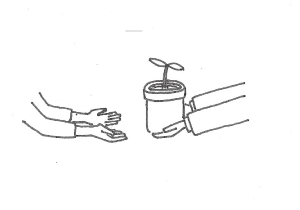
均一性
種を植えたら大体同じ植物ができるか。
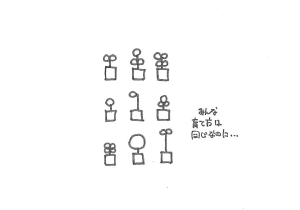
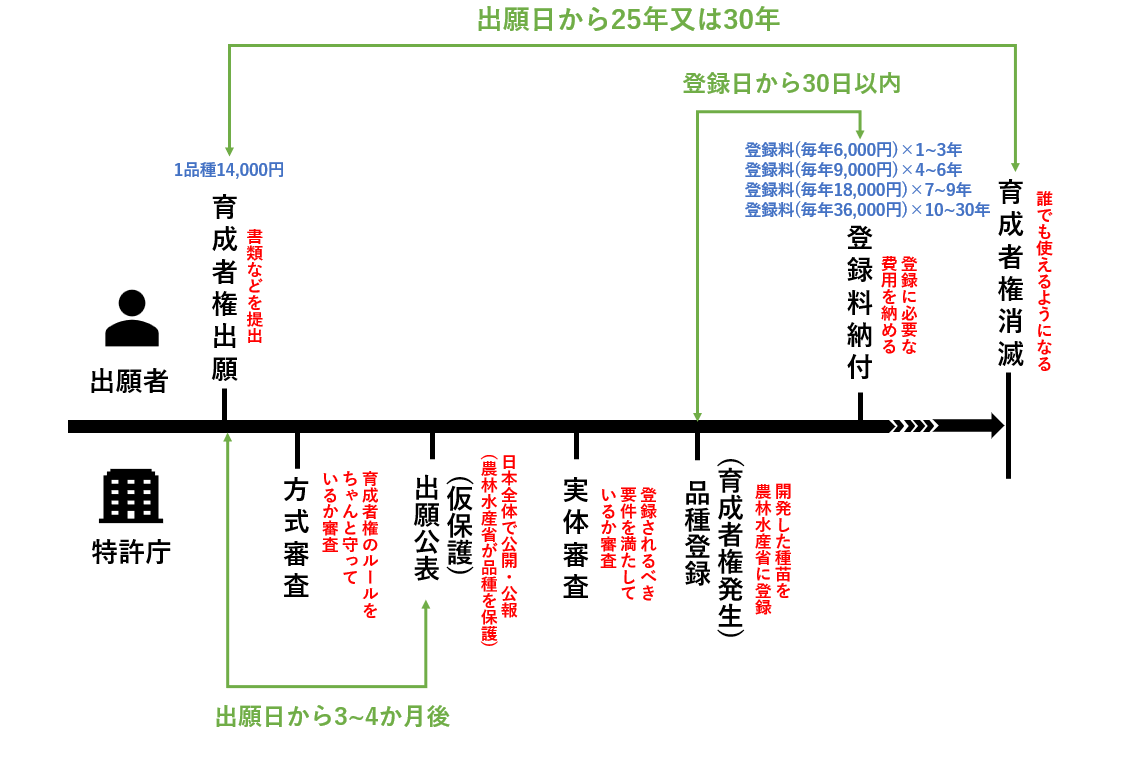
出願者は、農林水産大臣に品種登録出願をします。すると、すみやかに出願公表が行われます。拒絶理由があれば、意見書を提出する機会が設けられます。
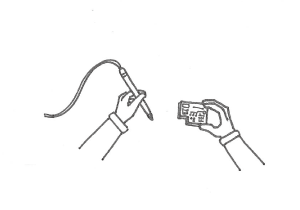 回路配置利用権とは、特定の回路配置を他の人や企業が使用する権利を指します。導体などの回路を作るためには製作者が苦労し作ったものです。簡単に真似されては開発した努力は水の泡です。そこで、回路の配置をまねされないために保護するのが目的です。経済産業省が管轄し、登録の日から10年まで保護されます。
回路配置利用権とは、特定の回路配置を他の人や企業が使用する権利を指します。導体などの回路を作るためには製作者が苦労し作ったものです。簡単に真似されては開発した努力は水の泡です。そこで、回路の配置をまねされないために保護するのが目的です。経済産業省が管轄し、登録の日から10年まで保護されます。
不正競争防止法は知的財産ではないかもしれませんが、非常に親和性の高い法律ですので、併せて学習をします。不正競争防止法とは、企業間でズルをしてお金を稼ぐことを防ぐための法律です。ズルしたものは差し止めや損害賠償を請求するルールがあります。不正とみなされる行為には以下のものがあります。

不正競争防止法では不正競争とはどんなものかが決められており、大きく10個に分けられています。
1. 周知表示混同惹起行為
広く知られている表示と、同じもしくは類似している表示を使い、その商品などと混同を生じさせる行為のことを言います。偽物を本物に見せようとする行為。
2. 著名表示冒用行為
他人の名前やブランド名を無断で使用し、あたかも自分のものであるかのように表示すること。
3. 形態模倣商品の提供行為
他社の製品の形やデザインをコピーして商品として出すこと。
4. 営業秘密の侵害
営業秘密を盗み、ばらまくこと。ラーメンのレシピを盗んで、SNSに書きこむなど。
5. 限定提供データの不正取得等
パスワードなどで守られているデータを盗み、使用する、または、他人に開示すること。ハッキングやフィッシングなど。
6. 技術的制限手段無効化装置等の提供行為
要はチートを使うことや、提供する行為をさします。
7. ドメイン名の不正取得等の行為
ドメイン名を不正目的で取得する行為。例えば、有名ブランドのドメイン名を先に取得し転売したりする行為。
8. 誤認惹起行為
商品などの原産地や内容などを誤解させる表示を使用すること。豚シューマイと思って買ったら、えびシューマイだったなど。
9. 信用毀損行為
周りの会社に嘘の情報を流して信用を無くす行為。
10. 代理人等の商標冒用行為
商標権を持っている会社や人の許可なく商標を使用すること。