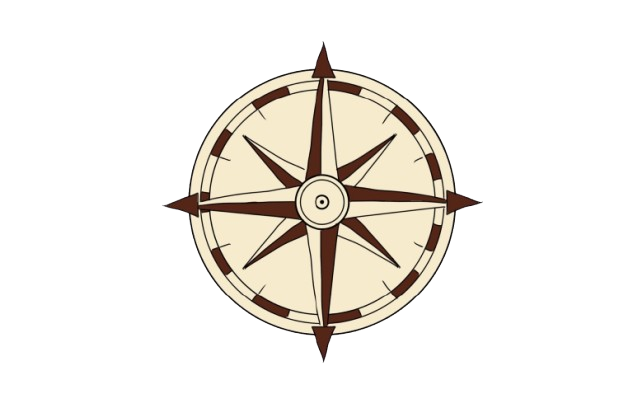
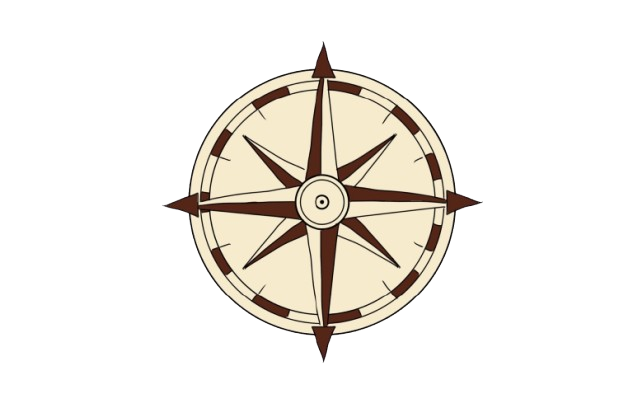
『ソラリス』は、ポーランドのSF作家スタニスワフ・レムが1961年に発表したSF小説。 レムの代表作であり、20世紀のSFを代表する作品と評価されている2004年に原題通りの『ソラリス』のタイトルでポーランド語原典からの完全翻訳版が国書刊行会より刊行され、2015年にハヤカワ文庫SFから出版された。 『惑星ソラリス』として1972年にソ連で、『ソラリス』として2002年にアメリカ合衆国で、計2度映画化されている。しかし、その両方に原作者のレムは不満を表明している。大 きな理由は、この作品の一番の意図が、人間が宇宙で出会うであろう知的生命体は、まったく人間とは異なるものである可能性があることを、象徴的に描くことであったからで、 だからタイトルも『ソラリス』なのであり、映画は2作とも、男女の愛や、過去への郷愁などが強調されたものになっているからとの意味のことを述べている。 理解不能な宇宙の神秘と、その前で立ち尽くす人間の存在、そして自己の内面を見つめざるを得ない状況を端的に表している。

時は未来。青と赤のふたつの太陽のまわりをめぐり、有機的な活動を見せる不可思議な海で覆われた惑星ソラリスは、発見されて以来、数々の謎を生んできた歴史があり、それは 「ソラリス学」という学問を誕生させるまでに至っている。そのソラリス上空に浮かぶソラリス観測ステーションで発生する奇妙な現象と「海」の謎を探るために心理学者のケルビンがあらたに派遣され、到着する。 ケルビンはまず、先任者の一人であるスナウトに会うが、なかなかまともな会話が成立しない。心理学者としてケルビンの先輩でもある先任研究員ギバリャンは自殺している。ケルビンは黒人の大女がステーション内を歩いているのを見る。もうひとりの先任研究員、自室に閉じこもりきりのサルトリウスの部屋には、小さな子供が走っているかのような様子がうかがえる。 ケルビンの居室にもほどなくして、10年前に自殺した恋人ハリーが現れる。ケルビンとハリーはかつて一緒に暮らしていたが、ある日喧嘩をし、ケルビンは家から出て行った。そ の去り際、ハリーは死んでやるとの意味の言葉をケルビンに投げかけたが、ケルビンは弱虫の君にできるわけがないとの不用意な意味の言葉を返してしまった。そのあとハリーは 死んでいた。そういう過去があったのだ。ケルビンの前にあらわれた「ハリー」はなぜ、自分がここにいるのか、どこから来たか知 らない。ケルビンは恐ろしさのあまり、「ハリー」を脱出用ロケットに乗せ、宇宙へ飛ばしてしまうが、また「ハリー」はケルビンの前に出現する。どうやら、それは、知的生命 体との仮説もあげられているソラリスの「海」が、ステーション内にいる人間の記憶から生み出すコピーであるらしかった。研究員たちが「客」と呼ぶ彼らは、一見人間のようだが、怪我をしてもすぐに再生する。が、一方では「海」が作っているのならば、「客」はソラリスを離れると消滅する存在ではないかと推測される。ケルビンはやがてオリジナルのハリーの死への自責の念に苦しみながらも、「ハリー」を愛するようになる。一方でステーション内の図書室でソラリス学の研究史をひもときなが ら「海」の真意を探ろうとする。「ハリー」の血液を検査したケルビンの発見にヒントを得て、サルトリウスらは「客」を 物理的に消滅させる方法を考案し、準備を進める。それはこちらの意識を(無意識ともにひっくるめて)X線にて「海」に照射して送るという方法だった。誰の意識(無意識)を 送るかはケルビンが選ばれる。その実験は成功し、「ハリー」は消える。ケルビンはむなしいような名状しがたい感情に襲われるが、実は、ギバリャンが残した音声記録をこっそり聞いた「ハリー」は、自分が「海」に作られた物質であること、ケルビンに苦痛を与えていることを知り、サルトリウスの装置で消滅させられることを自ら選んだということを、「ハリー」の別れの手紙から 知る。「海」は「客」を送り込むことで、敵とみなした人類に苦痛を与えようとしていたのか、 それとも好意を示そうとしていたのか、あるいはただ何かの実験、遊戯をしようとしていたのか。あまりにも人間とはかけ離れた存在である知的生命体である「海」の意図するこ とはいまだもってわからない。ステーションで「ハリー」とケルビンがつちかった愛情にはどんな意味があったのか。すべての理解への道は果てしないが、ケルビンは「ハリー」 喪失の虚無感を乗り越え、新たにこの未知の知的生命体とのあいだに起こる奇跡を信じ、期待して、ソラリスに残ることを選ぶ。
2026年の東京を舞台に、建築家の牧名沙羅が刑務所「シンパシータワートーキョー」の設計に携わります。AIとの対話を重ねながら、「同情すべき犯罪者」という新しい概念に違和感を覚える中、言葉の持つ本質的な意味や重みについて考えを深めていきます。実在の建造物と架空の建築物が混在する近未来の新宿で、AIが生成する「軽い言葉」と人間の創造性が交錯する物語が展開されます。『東京都同情塔』は、生成AIを活用して生み出された、革新的な芥川賞受賞作です。本作は、テクノロジーと人間性が交差する近未来の東京を舞台に、言葉の持つ力と社会への影響を鮮やかに描き出しています。SNSが当たり前となった近年、言葉を発端とするトラブルは後を絶ちません。本作で描かれる言葉への敏感さやAIが生成する文章への違和感は、そんな私たちの現状を反映し、独特の緊迫感をもって迫ってきます。本作はSF小説の枠を超え、私たちの未来に潜む可能性と危険性を映し出す鏡となっているのです。『東京都同情塔』は、AIや言葉との向き合い方を考えるきっかけを与えてくれるでしょう。〈AIと共創する新分野〉『東京都同情塔』は、芥川賞受賞作として初めて、人工知能(AI)と人間の協力で生まれた文学作品です。著者の九段理江さんは、ChatGPTをはじめとする「生成AIを駆使して作った」と語っています。作中では主人公の牧名沙羅とAIの対話が頻繁に登場し、その一部には実際のChatGPTの回答も採用されています。しかし九段さんは、AIの言葉を単に使うだけでなく、それを起点に物語を展開させました。AIが生成した「軽い言葉」への違和感が、物語の重要なテーマとなっているのです。この手法は、AIと人間の協働による新しい文学の可能性を示すとともに、言葉の重みや創造性の本質について読者に問いかけています。〈社会に与える影響〉この作品は、言葉が社会に与える影響を鋭く描き出しています。主人公の牧名沙羅は、建築家として「シンパシータワートーキョー」という高層刑務所の設計に携わる過程で、言葉の力に敏感に反応します。「同情すべき犯罪者」という概念やカタカナ語の氾濫に違和感を覚え、言葉が持つ本来の力や意味を見失っていく社会の姿に疑問を投げかけます。本作は言葉が人々の心理や社会構造に与える影響を深く考察し、読者に言葉の使用と解釈について再考を促します。このテーマは、情報過多やSNS、AIとの共存など、現代社会の課題と密接に結びついているのです。〈リアルな近未来世界〉『東京都同情塔』の魅力の一つは、リアリティのある近未来世界の描写です。2026年から2030年の東京・新宿を舞台に、現実とは異なる世界が展開されます。たとえばこの世界では、実現しなかったザハ・ハディド氏による新国立競技場(通称:ザハ案)が建設されています。この架空の建築物と「シンパシータワートーキョー」が新宿の街に共存し、現実と虚構が融合した独特の世界観を生み出しているのです。また、生成AIの浸透や、犯罪者の「同情されるべき人々」という再定義など、現代社会の傾向を極端に推し進めた設定が物語に緊張感と説得力を与えています。この仮想世界は、現代社会の問題点や可能性を映し出す「もう一つの現実」として機能しているのです。