


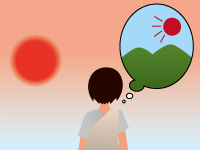
天気は人の生活の中に必ず存在し、大きく影響を与えるものであり、それを把握することはとても大事なことでした。紀元前650年にバビロニア人は雲のパターンから天気を予測し、紀元前340年にはアリストテレスが気象学に基づく天候のパターンを描き出しました。アジアでは中国人が少なくとも紀元前300年までに、天気を予測していたと言われています。
この時の予測は天候のパターンに頼るほかなく、その基準は人々の経験に基づくものでした。例えば、今でも言われている「日没時に空が際立って赤かったならば翌日は晴れ」などもそのひとつです。特に漁業者は天気予報が必要で、毎日空の様子などを観察していたそうです。


近代的な天気予報が発達したのは、1800年代のイギリスが最初でした。この頃、高速な通信手段として「電報」が開発され、ほぼ瞬時に広い範囲の情報を集めることができるようになりました。この情報のリアルタイム性は 、今の天気予報を伝える方法の原点となり、有用性の高さからイギリス艦隊も使用したそうです。その後、イギリスが気象庁を設置したのを皮切りに天気図を作成し、新聞で公開するなどの体制が整いました。

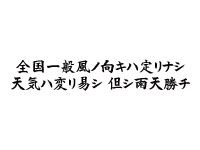
日本で初めて天気予報が発表されたのは1884年でした。当時の予報内容は1日3回、各県ごとではなく日本全国を一文で表したものを、東京市内の交番に掲示したものでした。1925年にはラジオ放送による予報が始まり、一般大衆にとってより身近な存在となりました。その後は第二次世界大戦の関係で一時発表が中断されましたが、終戦の2日後からラジオ天気予報が復活します。1953年にはテレビ放送、1955年には電話による予報案内サービスが開始されたりと、天気予報はその当時の情報伝達媒体によって、私たちの生活と深くかかわってきました。


通信と気象情報の調査技術が発達したことで、天気予報はとても身近な存在となりました。予測方法も過去のデータが蓄積されたことでより正確なものとなっており、これから時間が経つにつれてさらに正確になっていくと見られています。しかし、やはり大気の変化は複雑なものであり、未だ的中率は80%ほどしか無いそうです。