


各地の気象情報は陸・海・空から採取します。




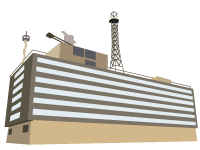
集められた情報は気象庁へと送られます。その情報を、気象資料総合システムを用いて整理します。

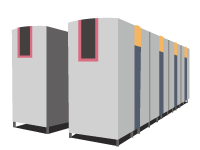
地球を細かい区分にわけ、それぞれの地点での気象データを求めます。不足した観測データを計算で補いながら、すべての区分にデータを与え、現在の地球の大気の状況をコンピュータ上に数値で再現し、数値予報を行ないます。この時の計算はスーパーコンピューターで行われ、短時間で多くの計算処理をします。

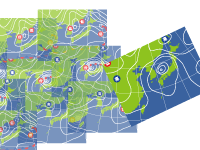
数値予報の結果を利用しやすい形にするために、数値予測の結果と実際の天気の過去の膨大な統計的なデータから、具体的な天気予報にする作業をします。


予報は予測する期間により、短期予報、週間予報、1ヶ月予報、季節予報などに分けられ、新聞やテレビなどの各メディアを通して情報を公開します。