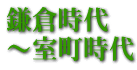源頼朝に始まる鎌倉時代は、武士階級が台頭し政治的実権を握った時代です。衣服も武士の生い立ちを示すかのように庶民服である狩衣が社会的向上をみたのです。また武士の平常服として直垂(ひたたれ)がありました。
女性の服装も儀礼的な裳や袴が省かれ、小袖が表にあらわれてきます。 室町時代の半ば以後はいわゆる戦国の世となり、群雄が割拠し、乱れた治世が続きました。日本の服装史の中でも最も貧困な時代であったといえます。しかしその中で桃山、江戸を経て現代へとつながる着物、すなわち小袖が単独の衣服として誕生しました。
平安末期から公家階級はしだいに没落の途をたどり、京都を舞台に十一年間も戦いに明け暮れた応仁の乱以後は、まったく勢力を失い、貴族服飾を維持することさえ困難となり簡易化され、武家や庶民服に近づいていきました。
対する庶民のほうは戦乱による不安と窮乏に追い詰められ、ついに土一揆をおこし、また下克上の風潮も高まっていったのです。
写真・図
鎌倉〜室町時代