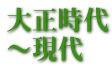大正時代は女子が職業を持つようになり、また洋行帰りの外交官婦人などから洋装が広まっていきました。和服のほうをみると、裾模様の訪問着が流行し、名古屋帯が考案されたのも大正九年頃といわれています。 昭和に入り、第二次世界大戦が勃発すると、服装はもとより、日常生活すべてが戦時色一色に塗りつぶされ、きものの空白時代を迎えました。国民服と標準服という実用本位 の服装が制定され、戦後の洋服時代を迎える基礎ともなっていきました。 戦後のきもの界は改めて振り返るまでもありませんが、敗戦後のわが国は新しい民主主義国家の建設がなされ、近代社会としての歩みをはじめました。室町、桃山時代から常に服装の中心に位 置していた小袖は、二十年にも及ぶ戦争と戦後の混乱の元にいったんは沈みながらも、現代にいたってなお生き続けています。 しかし現代のきものは、その内面においていろいろの要素を含み、変化をしていることも見逃せません。すなわち、もはや生活としてのきものではなく、晴れ着、くつろぎ着といったように着る目的によって細分化された性格を持つようになりました。洋服中心の生活の中で、時として触れてみたい、袖を通 してみたいといった存在、私たち日本人でも美意識の対象としていつもあるのがきものなのです。
大正時代〜現代