当事者の方
山岡吉男さん

インタビューにご協力頂きありがとうございます!本日はよろしくお願いします。
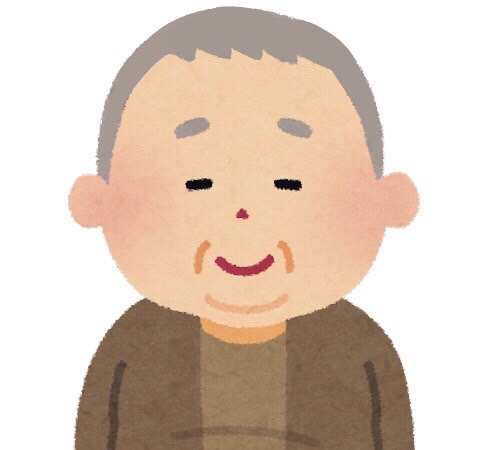
まずは自己紹介をしますね。私はハンセン病を患い、高校を卒業してから長嶋愛生園に入所しました。今はまた別の療養所である多摩全生園に入所しています。

今日は入所者の方にしか聞けない質問をいくつか用意してきたので早速質問させていただきます。
まず、ハンセン病を患った際、ご両親はどのような反応だったのでしょうか?
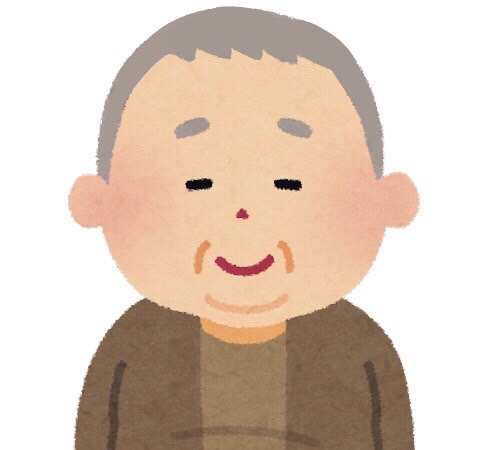
はい。両親はやはりハンセン病は怖い病気だと認識していました。そのため、お風呂は最後だったり、茶碗を別にされたりなどでしたね。なので、家族との絆があまりなく他人のような感じでした。今でも家族との縁は薄い状態です。

なるほど。ありがとうございます。

では、次の質問です。ハンセン病が流行してから、年月が経ち、治療薬がつくられましたが、治療薬ができたことでの変化などは何かありましたか?
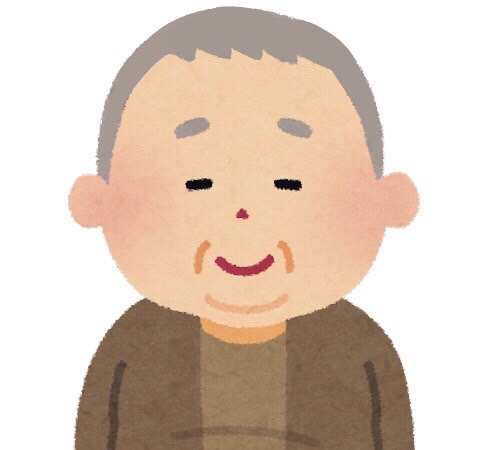
外に出られるようになりました。しかし、それでもまだ白い目で見られることもあり、船から降りると嫌な目をされることもありました。

山岡さんはそういった差別や隔離についてどのように考えていましたか?
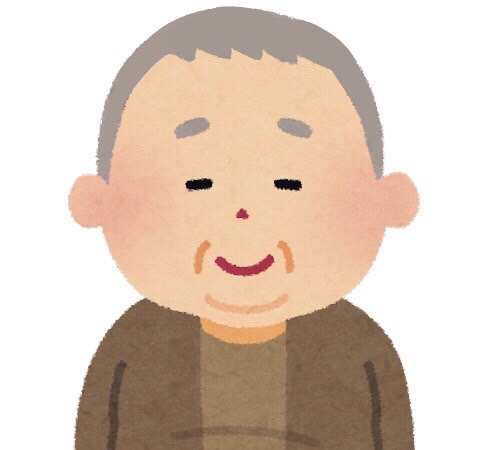
あまり眼中になかったです。一刻も早く病気を治して、普通に暮らしていきたいという気持ちでいっぱいでした。

ありがとうございます。では、療養所の雰囲気はどのようなものなのですか?
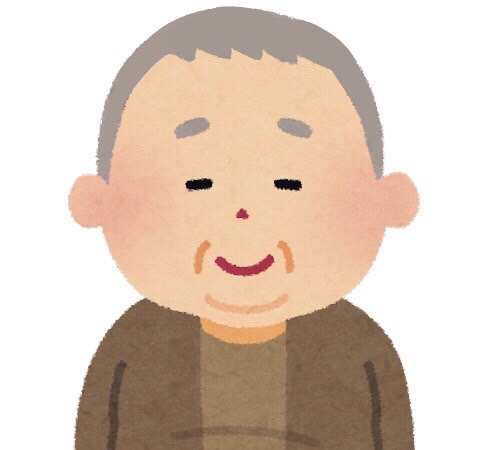
あまり多くを語らない人が多いです。未だに園内で偽名を使う人もいたりします。家族との繋がりがない人のほうが多いですね。ですが、やはり中にいる安心感や園のアットホームな雰囲気にはかなり助けられていて、自分の居場所は園しかないと思います。看護の方が家族のようなものですね。

園での暮らしについてもう少しお話を伺いたいです!
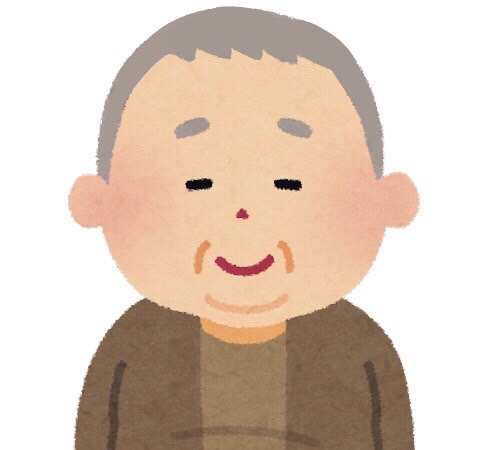
はい。園には娯楽も多く存在していますよ!海や山に行ったりなどもしますし、年間で行事がいくつか用意されているので、それも楽しみの一つです。

とても面白いですね!いつかぜひ実際に見てみたいです。

では、最後の質問です。今の若者に伝えたい思いやメッセージはありますか?
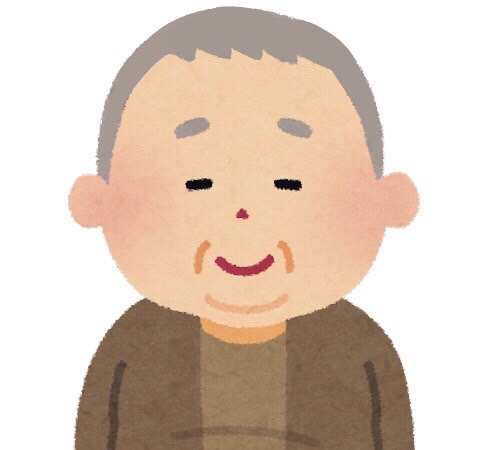
はい。今の若い人たちは、色々なことを勉強して理解してもらいたいです。資料館に行くだけでなく、色々な所で学んでほしいですね。そして、コロナウイルスより楽であると知ってほしいし、安心して接してほしいです。
今後も色々な人たちに語り継いでいってもらいたいです。

ありがとうございます。しっかり自分から学び、理解を深めることが大事だとわかりました。

本日はとても貴重なお話をありがとうございました!今日学んだことを探究活動に生かしていきます!
竪山勲さん
- ハンセン病は竪山さんにどのような影響を及ぼしたのでしょうか?
- 母がハンセン病でしたが、誰もその事を教えてくれなかったため何故自分たちの家族が周囲に避けられているのかが分かりませんでした。そしてハンセン病は家族をも離別させるということがわかりました。
- ハンセン病の理解がまだ広がっていなかった頃の園での強制隔離とは、一体どのようなものだったのでしょうか?
- マラソンや土木作業、クリーニングなどをはじめとするきつい運動をたくさん強いられ、死なせようと途絶えさせようとさせられていました。園は孤島にあるため逃げ出す事も出来ず、やりたいと言ったことも全て職員の人に押さえつけられていて、教育の場であるはずなのに差別が絶えなかったです。
- らい予防法の廃止についてはどのように思いましたか?
- らい予防法の廃止はあくまで表面上の廃止であり、問題の根本的な解決には至っていませんでした。謝罪に関しても、らい予防法の廃止が遅れたことに対するもののみであり、差別的な内容への謝罪ではなかったのです。
- ハンセン病の現状はどういったものでしょうか?
- ハンセン病で亡くなってしまった方々の無念の涙を無駄にしないよう、間違いを正すことが市民の責務ですね。1度回復しても療養所に再入所する方も多く、差別偏見は未だなくなっていない現状であり、まだまだ問題は多く残されていると思います。
柴田スイ子さん
- ハンセン病にかかり、どのような苦悩を抱えていたのでしょうか?
- ハンセン病を人に言うことが出来なくて、銭湯に行くことすらかなりの覚悟が必要でした。また後遺症が酷かったため、何年もかけて少しずつ整形を繰り返していました。
- ハンセン病患者の方が通う学校とはどのようなものだったのでしょうか?
- 一概にハンセン病患者と言っても症状の重さはもちろん人によって異なり、自分は症状が重かったため、周りの人をみてなぜこんなに症状が軽い方がいるんだろうと思ったりもしていました。しかしやはり生活を制限されていた身としては、学校は楽しい場所でしたね。
- ハンセン病の裁判で勝訴した後、なにか変化はあったのでしょうか?
- ハンセン病について知ってくれる人が増えましたね。以前よりかなり過ごしやすくなり、少しずつ変わっていったような気がします
- ハンセン病について、語り継いでいきたいことはなんですか?
- 病気について、「もし自分だったら」という自分事として考えて欲しいということですかね。
中尾神治さん
- ハンセン病にかかり、家族との関係はどのように変化していったのでしょうか?
- 家族を差別や偏見から守るため「名前を変えた方が良いか」と聞いたところ、名前を変える必要はないと言われました。しかし、兄が結婚していて子供もいたため、「もう家には帰ってこないでくれ」とは言われました。家族を守るためには仕方のないことですが、故郷に帰りたいという思いは強かったですね。
- ハンセン病患者への差別とは具体的にどのようなものがあったのでしょうか?
- お店でコーヒーと言って醤油を出されたり、食事をしようとすると「閉店です」と言われて店を追い出されるなどですかね。ひどいものです。
- なぜ今このように語り部活動をされているのですか?
- 最初はやはり話すことに対して抵抗がありましたが、まだハンセン病をよく知らない人たちに話すことで差別をなくしたいと思うようになりました。全てをさらけ出し、病気のことを知ってもらいたかったのです。今でも色々な工夫をして、多くの人に興味を持ってもらえるようにしています。
森和夫さん
- 大島青松園は森さんにとってどのような場所なのでしょうか?
- 「第2のふるさと」と言うけれど、ふるさとよりも住んでいる時間が長い大切な場所。
- ハンセン病にかかってしまったことで、周囲の方はどのような反応をしていましたか?
- 小学校では登校を禁止され、何度も職員が家を押しかけてきました。友達からも嫌悪されていて、なんとか学校に行っても、先生達は白ずくめの防護服を着ていたのを覚えています。
- ハンセン病は森さんにどのような影響を及ぼしたのでしょうか?
- 外に出ることが怖くて買い物があまり出来ないため、園の職員の方に代行してもらっています。また人との関わりがどんどん減ってきていて寂しいですね。
- 当時の医療はどのようなものだったのでしょうか?
- 当時は医者もハンセン病に対する薬の理解がまだ足りておらず、注射を熱湯消毒して何回も使い回ししたりしていました。
- ハンセン病のこれからについてどう思いますか?
- これからも出来ることは維持、継続をしていかなければならないですよね。今後も私達がどのように差別や偏見を受け止めていくかを考えていく必要があると思います。
佐藤勝さん
- ハンセン病は佐藤さんにどのような影響を及ぼしたのでしょうか?
- ハンセン病になったことで、夢や希望が打ち砕かれました。生きる目的や楽しみが一気になくなったんです。
- 療養所で過ごす中で大変なことはどのようなことでしょうか?
- 冬の時期の雪かき。比較的動ける元気な人が屋根の雪下ろしをしますが、これが中々危険な作業で、中には命を落としてしまう人もいますね。
- 現在佐藤さんはどのような活動をしているのでしょうか?
- 保養園で唯一の語り部活動をしてます。
- 佐藤さんが今思っていることはなんですか?
- ハンセン病で不自由になってしまった人に対する差別や偏見をなくして欲しいですね。ハンセン病を知らない人に理解して欲しいのはもちろん、当事者の方々も後遺症がある人ほど助け合いをして欲しいです。







