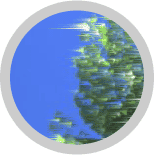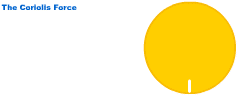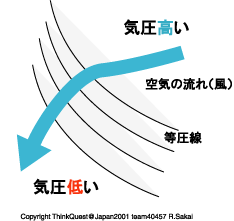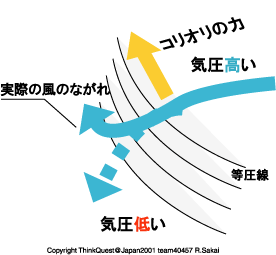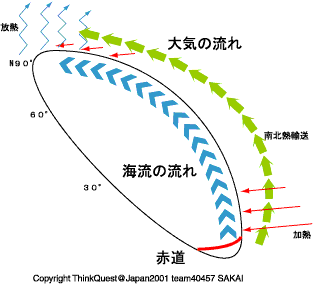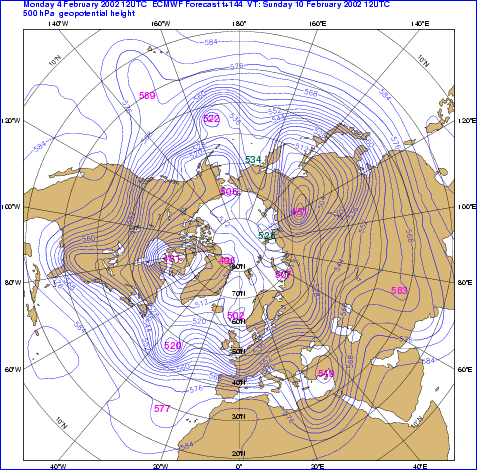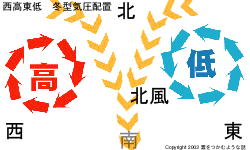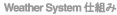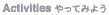|
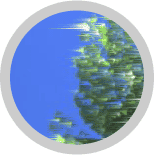
コリオリの力
地球は自転しているため、地球上では、まっすぐに動くはずの物はその進行方向が曲げられます。この進行方向を曲げる力をコリオリの力(転向力)と呼びます。 
地球に固定されたものは、宇宙空間に固定された人から見れば地球の自転とともに回転していることになる。したがって、例えば北極から真南に向かって発射した物体は、宇宙から見れば最初に発射して方向にまっすぐに飛んでいって着地するわけだが、その間に地球が自転するため、物体が到着した地点は最初の目的地点よりにしにそれるはずである。宇宙にいる人から見れば、それは地球が自転しているからにしにそれたのだということは明白だが、地球上面にいて地球とともに回転している人からみれば、その物体に何か力が作用した結果進行方向に対して右にそらせられたのだということになる。このような、見かけの力をコリオリ力(転向力)という。
天気予報の技術 天気予報技術研究会著 東京堂出版から引用
風は気圧の高い方から低い方へ吹くと前に説明したが、この風に対しても、例外なくコリオリの力は働く。本来、風は 図のように気圧の高い方から低い方へ吹くはずである。 図のように気圧の高い方から低い方へ吹くはずである。
しかし、コリオリの力によって風は進行方向を曲げられて、 図のように等圧線と平行な向きに吹くことになる。この風のことを地衡風とも呼んでいる。 図のように等圧線と平行な向きに吹くことになる。この風のことを地衡風とも呼んでいる。

地球が太陽から受ける熱量は赤道付近(低緯度地方)が最も多い。一方、極付近(高緯度地方)では太陽高度が低く地球が太陽からの熱量が少なく、宇宙空間に熱が逃げている。赤道付近で受けた過剰な熱は、海流や大気の大きな流れによって熱が不足している極地方へ運ばれる。これによって、緯度による熱収支のアンバランスが解消されている。

偏西風
日本の上空約12〜16kmには、偏西風と呼ばれる強い西風が吹いている。偏西風はジェット気流とも呼ばれ、蛇行しながら北極を囲むように環状に流れている。
 図にあるように等圧線同士の間隔が狭いところが強い西風が吹いていることを示している。北極を中心に等圧線が波打っている。この偏西風のうねりを偏西風波動という。この偏西風波動は、日本付近の低気圧・高気圧の形成に重要である。詳しくは低気圧のページを参照されたい。 図にあるように等圧線同士の間隔が狭いところが強い西風が吹いていることを示している。北極を中心に等圧線が波打っている。この偏西風のうねりを偏西風波動という。この偏西風波動は、日本付近の低気圧・高気圧の形成に重要である。詳しくは低気圧のページを参照されたい。
 低気圧 低気圧
 偏西風の画像は風のことReferencesで入手可能 偏西風の画像は風のことReferencesで入手可能

大気の大循環
地球の熱収支のアンバランスを解消する一つの機構に大気の大循環がある。これは、地球規模の大気の循環で、地球の気象現象に大きな影響を与えている。夏と冬では地球が太陽から加熱される場所が異なるので、夏と冬で循環の強さが変化する。
 赤道付近で暖められた大気は上昇して、上空で極方向へ向かって流れ北緯(南緯)30°付近で下降して地表近くで北東貿易風となって赤道へ戻ってくる。これをハドレー循環と呼んでいる。 赤道付近で暖められた大気は上昇して、上空で極方向へ向かって流れ北緯(南緯)30°付近で下降して地表近くで北東貿易風となって赤道へ戻ってくる。これをハドレー循環と呼んでいる。
北緯(南緯)30°以上の中緯度付近では、偏西風の南北への波動(波打つこと)によって熱の輸送が行われる。この図では概念的にフェレル循環としている。
 この偏西風の南北への蛇行(うねり)を偏西風波動と呼ぶ。 この偏西風の南北への蛇行(うねり)を偏西風波動と呼ぶ。
高緯度地方でも熱収支を解消するように極循環が生じているが、循環は弱い。

モンスーン(季節風)
大気の大循環によって引き起こされる大気の流れは、季節によって変化します。この変化によって生み出される季節ごと、特に夏と冬で大きく変化する変化する地球規模の風をモンスーン(季節風)と呼ぶ。
モンスーンは世界各地で見られるが、中でも顕著なのは夏にインド・東南アジア・日本にかけてみられるアジアモンスーンである。
アジアモンスーンは、加熱されたインド洋からの湿った空気がユーラシア大陸へ向かって吹き込み各地で雨を降らせる現象である。
インド洋を北上すると、途中にヒマラヤ山脈があり、山脈を越えるために一端モンスーンは上昇する。このときに、冷やされた水蒸気が凝結して余った熱がエネルギーとして生じる。この水蒸気の凝結にともなう熱が地球の熱収支の過不足を補填する重要な要素である。
 雲のこと 雲のこと

西高東低・南高北低・北風
日本で、冬にみられる季節風(北風)はシベリア高気圧(寒冷なシベリア気団)と北太平洋上のアリューシャン低気圧の間に形成される気圧の高低によって引き起こされる。日本を中心に見ると、この気圧配置は 西高東低となる。夏は小笠原高気圧(気団)が南で発達するので南高北低となる。 西高東低となる。夏は小笠原高気圧(気団)が南で発達するので南高北低となる。
小笠原高気圧(太平洋高気圧)
夏(北半球が)には赤道付近が激しく加熱されるので、赤道の熱を直接運ぶハドレー循環が強くなる。上空のハドレー循環の流れが下降する地点では、下降気流によって高気圧帯(帯状に東西にのびる高気圧)が生み出される。夏にハドレー循環が強くなることによって作られる強い下降気流が形成する巨大な高気圧帯は、日本で小笠原高気圧(太平洋高気圧)と呼ばれている。
 小笠原高気圧は夏、日本に熱く湿った南風をもたらす犯人である。小笠原高気圧(大平洋高気圧)が発達している期間は、台風は高気圧帯に進入できず高気圧帯の縁に沿って移動します。よってこの高気圧に覆われている時期の日本へは台風はやってこられない。 小笠原高気圧は夏、日本に熱く湿った南風をもたらす犯人である。小笠原高気圧(大平洋高気圧)が発達している期間は、台風は高気圧帯に進入できず高気圧帯の縁に沿って移動します。よってこの高気圧に覆われている時期の日本へは台風はやってこられない。
 高気圧 台風 高気圧 台風
|