ねつ造
完全に虚偽であり、人を騙し損害を与えることを目的としているもの。事実とは違う情報を0から作り出し、楽しみや宣伝のために使われるものを指します。
他のグレードと違い相手を騙すために悪意を持って作成されているものであり、さらに真実の情報が含まれているわけでもいないため、8つの手口の中で最も悪質なものです。それ故、数あるフェイクニュースの中でも被害がより大きく、最も注意が必要な項目です。
日本に置ける事例
今やTwitterなどのSNSは世間に多く広まり、個人の意見や個人で手に入れた情報を全国、全世界に発信することが可能になっています。特に震災時など世間が大きく混乱している時にはSNSは大きく活用され、必要な情報を被害にあっている人々等に多くの情報を届ける事が出来ます。しかし、個人で情報を簡単に発信できるということは、それが真実かどうか碌に確認せずに情報を発信できるということです。また、混乱している状況で入ってきた情報が真実かを確認すること等難しいこと。それ故、災害時などでは特に個人が発信した偽の情報が拡散されてしまうことも少なくありません。
< 災害時にTwitterで偽の情報が投稿、広く拡散され多くの人の混乱を招いた事例 >
2016年4月、九州地方熊本県周辺にて大地震が発生したことはまだ記憶に新しいことでしょう。震度7の地震という巨大な災害であったため当時被害を受けた人々は混乱し、地震に関連する情報を得ることで、自身の置かれた状況や家族の無事など様々なことを知ろうとしていました。その中でもSNSは常に最新の情報が更新されているため、多くの地域で活用されており、特にTwitterは当時から大手SNSとして広く活用されていたため、多くの人々がTwitterから情報を得、また得た情報を次々とTwitterで拡散していきました。数年に一度レベルの地震だったため、必然的にSNS、Twitter上に上がる情報も多くなります。そしてSNS上の情報というものは上にも書いた様に個人発信の情報であることが多いため、当時は幾数ものフェイクニュースがネット上に飛び交っていました。そしてそんな中、写真とともにとある一つのツイートが投稿されました。
「地震のせいでうちの近くの動物園からライオン放たれたんだが 熊本」
信号が日本にはない形である、撮影者とライオンの距離が近すぎる等、落ち着いてよく写真を見たならばこのツイートがフェイクであることは一目瞭然でしょう。そもそも、大きな地震程度で猛獣が逃げ出してしまうような動物園は有り得ないでしょう。しかし、この時の世間は熊本地震の影響で大混乱の最中。さらに、普段ネットやSNSを頻繁に利用していない、インターネットに慣れていない人々も最新で多量の情報を求めてTwitterを閲覧している状況。そんな中投稿されたこの情報はSNS上の人々に大きな不安と混乱を与え、また情報を閲覧した人々は正義感をもって、または面白がってこの情報を拡散しました。一度拡散されるとより多くの人に閲覧され、またさらに情報が拡散される。そうしていくうちにこの情報は2万回以上ものリツイート(拡散)が行われるまでに至りました。
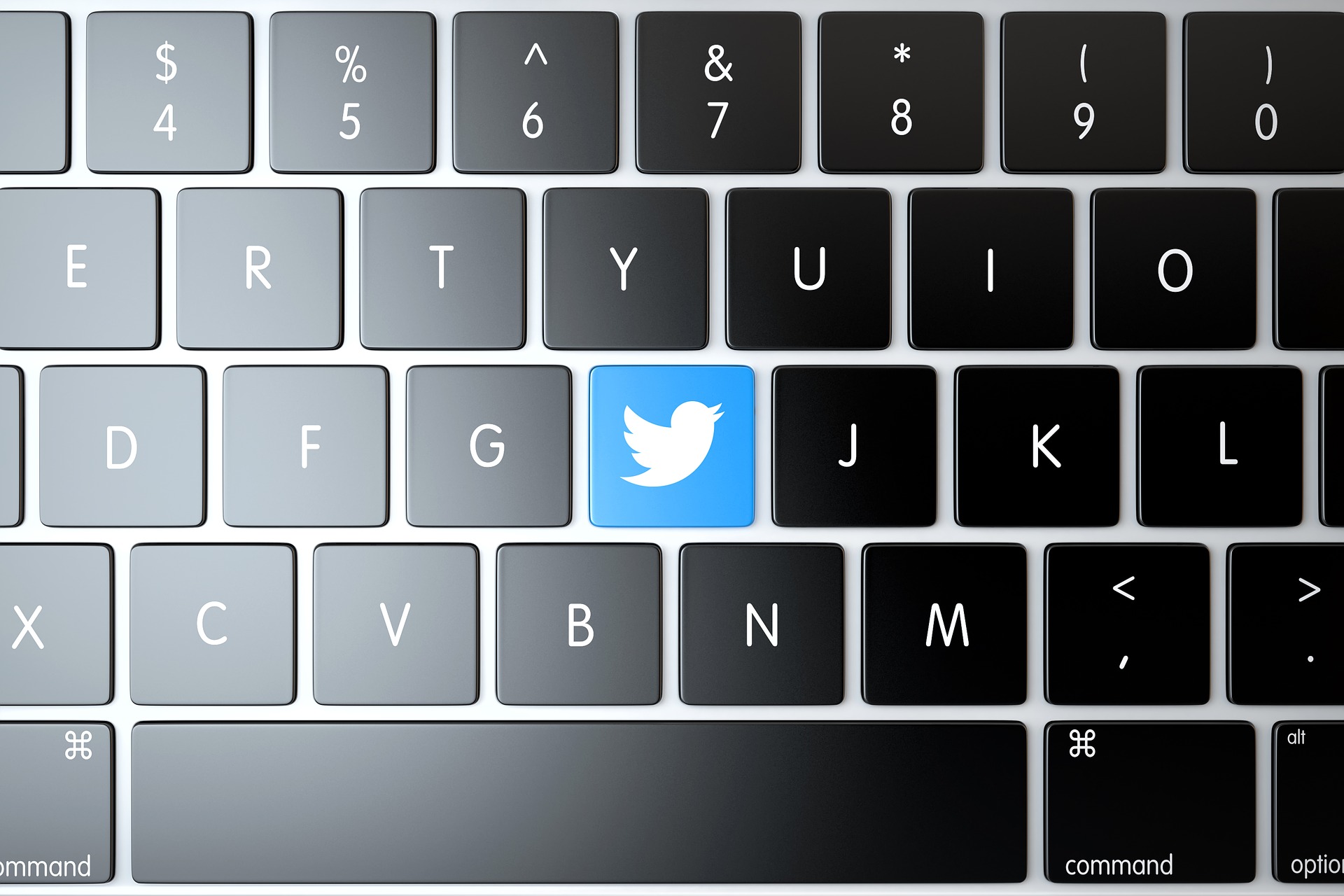
このツイートは、よく考えればすぐに偽だと分かるものであり、また冗談半分で投稿されたものなどそこまで攻められる謂れはないと考える人もいるかもしれません。しかし、その冗談半分の情報でも、場合や状況により時に大きな影響を及ぼしてしまう可能性が少なくない事は容易に考えられる事でしょう。実際、この投稿を受けて熊本県に建っている熊本市動植物園には百件超の問い合わせが殺到し、園自体への地震の影響への対応に忙しいなか電話応対に時間を割かざるを得なかったそうです。そして、このツイートを投稿した当人は偽計業務妨害により逮捕されるまでに至りました。このフェイクニュースがここまで広がり被害を拡大させてしまった要因として、勿論面白半分で偽情報をばら撒いた投稿者が最も悪質でしたが、いくら緊急事態であろうとも情報の真偽を確認せず安易に情報を拡散してしまったことも挙げられます。インターネット、SNS上で上げられた情報を拡散する際は、拡散したからには自分も第三者ではなくその情報を世に発信する人となるという意識を持つことが大切です。
海外における事例
その情報が正しいものであると一度認識してしまった場合、その思い込みを変えることは簡単ではありません。特に、その情報に対して自分と同じ考えである人々が多くいる場合さらに思い込みは悪化し、考えを改めることは難しくなります。そんな思い込みは知事や国会議員などの人を纏める立場の人々にも起こり得ることであり、特に、大統領などの国家内で立場の高い、正しい方向を向いていなければならない人々が誤った情報を信じている場合、その下に着く人々やそれ以外の国民までもが思い込みを強め混乱を引き起こしてしまうことさえあり得ます。
< ウイルスの影響を少なく見せるため偽のニュースまでも作り出した事例。 >
新型コロナウイルス感染症が流行し始めた当時、世界各国の中には感染症の影響を軽んじて、また経済活動を中止することによる影響を感染症による影響より重く考えて、感染症への対策を多くは行わなかった国も多々ありました。その中でも特にブラジルは新型コロナウイルスへの対策を当初は一早く行っていたにも関わらず、経済を重要視する大統領の考えにより感染対策を取りやめ、その結果感染者は膨れ上がってしまいました。その後、事の重大さを理解した政府が感染症への対策を開始するも時すでに遅く、ブラジルは世界有数の新型コロナウイルス感染症感染国へと変貌してしまいました。

当時ブラジルで感染症対策が必要だと強く訴えていた人々の根拠の一つとして、既に病院には新型コロナウイルス感染症の感染者が溢れかえっており、「医療崩壊」が起こっているという事実が存在しました。ところがそれに対し、大統領の意見に従う、つまり新型コロナウイルス感染症対策よりも経済を優先する意見の国会議員達は、患者のいないベッドや人のいない病室を移した映像により、医療崩壊やそれに準ずる事態等起きておらず人々が普段の活動を自粛するほど新型コロナウイルス感染症は脅威ではないと意見を述べ、対策を徹底するよう強硬に訴え続ける人々の方が誤った情報を提供していると主張しました。
ところがこの主張が公開された後、その映像が臨時に作られた病院、さらに開院前で内部を清掃している最中に撮影された事が判明しました。開院前の病院になど患者が一人でも居るはずがありません。この主張は根拠が捏造されたものであり、フェイクであったことが分かります。この事態に対し、感染対策を進めることを推奨している知事や議員は憤りを表すコメントを残し、対策を怠ることを主張する人々が主張したものはフェイクニュースであったこと、そして医療現場は余裕などまるであらず常にひっ迫している事を強調しました。この事例の他にも、この対立の渦中では両方の主張の陣営が様々な意見、様々な情報を根拠として主張し、多量のフェイクニュースも飛び交いました。幾ら立場の高い責任の高い立場の人々でも自分の主張を通すためにはフェイクを通してしまう場合もあること、それを意識しておくことも、大切かもしれません。

まとめ
この項で扱ったものは、数ある捏造されたフェイクニュースの中でも比較的被害の軽い部類な物です。このグレードに当てはまるフェイクニュースの中には、人の命さえ左右してしまうものも存在します。しかしそんな軽い部類の物でも、かなり被害が拡大してしまう悪質なものが多いと分かるでしょう。特に、日本に置ける事例で紹介した例のようなものでは遊び半分、冗談半分でフェイクニュースを投稿し、それでも大きな被害を呼んでしまうこともあります。当然のことですが、たとえ遊びであろうとも、それが被害が少ないものだとしても、フェイクであると分かって情報を発信することは何が有ろうともやってはいけません。また、情報を発信する側としてだけではなく情報を日々受け取る側としても、まずは、情報発信者に何の利益もなくともその情報が確かな信頼のおけるものであるかを確かめて情報を受け取ること。そして何より、情報を拡散する際には、自分は情報を受け取る側ではなく既に情報を発信する側になるということを意識し、発信する情報の真偽を判断することを怠ってはいけません。
関連記事