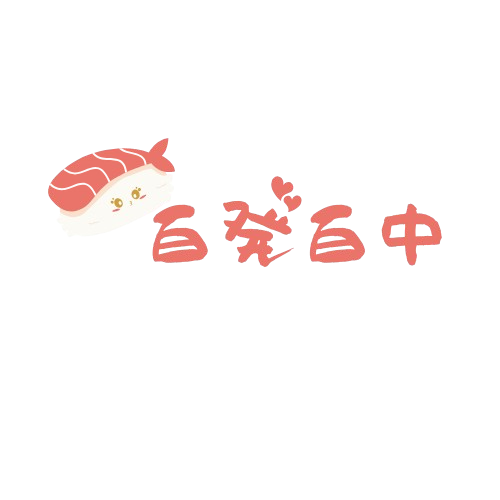インタビューのまとめ
TAKEO株式会社さんでは昆虫を「原型のままのもの」からタガメサイダーのように「エキスを抽出したもの」まで様々な昆虫食の開発を行っていることがわかりました。開発目的は一般的な食材と同じように昆虫が食として楽しまれるようになるためということでした。昆虫食を食べる習慣がなかった人たちが地球環境の観点などにより興味や関心を持つように開発がなされていると感じました。
陸えびJAPAN株式会社さんではコオロギの養殖の詳細を知ることができました。コオロギは省スペースで一年中飼育でき、これからのたんぱく源として非常に有効だと感じました。
長野県では昔からイナゴ、カイコの蛹、蜂の子、ザザムシが食べられていて、現在でも それらが一般的に販売されていることがわかりました。しかし、50代以下の年齢の人は食べる習慣がないこともわかり、昆虫を食べる習慣が根付いている長野県でさえも昆虫食離れが進んでいると感じました。
1950年頃の山形県ではイナゴやタニシを捕まえて家庭で調理し、たんぱく源として食べていたことがわかりました。しかし、現在では昆虫の数が減少したため食べる機会がなくなっていました。その背景には、強い農薬の散布や産業の衰退があることがわかりました。
インタビューをして、昆虫食が根付いている地域では、昆虫は食べるために養殖されたものではなく、自然との共存の中で生まれた伝統的な食文化であることがわかりました。それは、近年の昆虫食とは大きく異なる部分であり、昆虫食は「自然」から「飼育」へ、「獲って食べる」から「買って食べる」へシフトして行っているのだと感じました。そして、たんぱく質不足や深刻な飢餓を解決するには昆虫食は養殖が必須になると考えました。
しかし、このことが販売価格へ大きく影響していると感じました。日常の中に昆虫食がある山形県や長野県ではイナゴの佃煮75g(約90匹入り)は298円なのに対し、TAKEO浅草本店では乾燥イナゴ15g(約100匹入り)は1,280円と価格に差があり、養殖には課題があると考えます。しかし、陸えびJAPAN株式会社さんのような養殖が一般的になれば省スペースで時期を問わないため、価格の低下に繋がるのではないかと考えました。
現在は、昆虫を食べる習慣があった地域では昆虫食離れが進み、食べる習慣がなかった地域では興味を持つようになっていることがインタビューを通してわかりました。そして、今後どのようにすれば積極的な購入に繋がるのかを考える機会になりました。
インタビューにご協力いただいた皆様ありがとうございました。