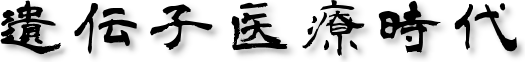エラーの修復機構
ヌクレオチドが繋がり、新たなDNA鎖が合成されるとき、絶対に間違いが起こらないとは言い切れません。
誤ったヌクレオチドが結合する可能性を常に孕んでいるからです。
可能性があるとはいえ、間違いがそのまま残されてしまっては大問題となります。
そこでDNAを合成する酵素「DNAポリメラーゼ」の出番です。
DNAポリメラーゼには、塩基配列の誤りを見つけ、修正できる機能(酵素活性)があるのです。
例えば、新しいDNA合成が行われるときに、DNA鎖の端で相補結合出来なかった部分があると、DNAポリメラーゼはこの部分のヌクレオチドを鎖から切り離し、処理します。
そして正しいヌクレオチドを結合させてから、DNAの合成の続きをします。
つまりDNAポリメラーゼは、新しいDNAを合成すると同時に、塩基配列にミスがないかどうか、校正の作業を担っているわけなのです。
このことから、この機能を「校正読み」の活性と呼ぶこともあります。
また、新たに合成されたDNA上に相補結合しない箇所があったときには、DNAに切れ目を入れる酵素により、相補結合していない部分の周囲も含めて、DNAの一部に切り込みが入れられます。
そのあとDNAポリメラーゼが、切れ目の所から問題の部分を切断して除去し、その部分に新しくDNAを合成することでミスを正します。
つまりミスを切り取ってから修復するわけで、これは「切り取り修復」の活性と呼びます。
このような具合で、生物の細胞内では、塩基の相補結合以外にもいろいろな仕組みを使うことで、DNAの正確さが保っています。
Design by