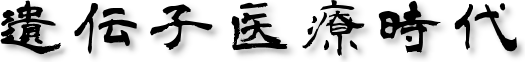幹細胞
「ES細胞」や「iPS細胞」という名前は皆さんも一度は聞いたことがあるでしょう。
ところで皆さんはES細胞やiPS細胞のES,iPSが何を指しているのか知っていますか?
ES細胞には「胚性幹細胞」という名前が、iPS細胞には「人工多能性幹細胞」という日本語の名前があります。
どちらの名前にも「幹細胞」という言葉が含まれていますね? ここではその「幹細胞」について説明していきます。
生物を構成する細胞
生物にはアメーバやゾウリムシなど一つの細胞からなる「単細胞生物」と私たち人間などをはじめとする「多細胞生物」が存在します。
前のページでも説明したように私たちは細胞分裂、分化、成長を繰り返して体を形成していきます。
分裂、分化、成長という働きをすべて一種類の細胞が行っているかというと実はそうでもないんです。
多細胞生物を構成している細胞は大きく分けて三種類あります。それぞれ「分化細胞」「TA細胞」「幹細胞」という名前が付けられています。
分化細胞はその名の通り分化して心臓や筋肉などさまざまな器官に変化していく細胞のことです。
実は、大部分の分化細胞は増殖していません。そのためTA細胞が代わりに増殖することによって体が維持されています。
しかしTA細胞には分裂回数に限りがあり、TA細胞には自己複製能力がないため、体を維持するためにはTA細胞を生み出してくれる細胞が必要となります。そこで登場するのが幹細胞です。
幹細胞とは
幹細胞とは一般的に自己複製能力と分化能を兼ね備えた細胞とされています。
つまり、時には自分自身と全く同じ細胞を複製し、時には分化して別の細胞(主にTA細胞)を作り出す細胞のことです。
分化細胞やTA細胞の分裂回数には限界がありますが、幹細胞は半永久的に増殖することができます。
多細胞生物の体は「分化細胞」「TA細胞」「幹細胞」の三つの細胞が支えあうことでその形を保っています。
再生医療の一環として病気やけがの治療にも幹細胞は用いられています。
再生医療への活用
一般的に成体の体内に存在している幹細胞は分裂が遅いのですが、これを体外へ取り出して効率よく増殖させる研究が盛んに行われています。
患者さん自身の組織から採取できる体性幹細胞は、倫理的な問題も少ないうえ拒絶反応の心配もありませんので、細胞移植医療における重要な細胞ソース(移植細胞を採取する源)として期待されています。
※ドナーと遺伝子型の近い患者さんに対する骨髄移植なども、すでに実用化されている体性幹細胞移植の一種と言えます。
体性幹細胞を体外で増殖させる際に自己複製能と分化能をいかにして維持するのかということが研究の大きなポイントになっているのですが、これが結構難しく、難航しています。
遺伝病の患者さんに細胞医療を適用する際、細胞バンク由来の細胞を用いず、患者さん自身の細胞を用いた場合、遺伝病を根治するためには遺伝子治療が必要となりますが、遺伝子治療では、増殖能の高い細胞が必要となります。
しかし先ほども述べたように成体由来の体性幹細胞は、体外で多量に増殖させるのにはなかなかうまくいっていません。
一方ES細胞やiPS細胞は、体性幹細胞と比べてよりいろいろな器官への分化能を有するだけでなく、体外で多量に増殖させることが可能なので、将来の細胞移植医療における細胞ソースとして注目されているのです。
Design by