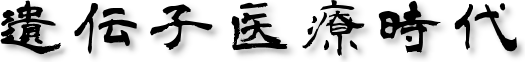DNAの個人差
ヒトのゲノムには個人差があります。
染色体が他の人とは違っているような大きな違いから、STRと言われる配列の繰り返し方の違いなど、多種多様です。
このゲノムの差が、人と人との違いをつくる一つの要素です。
SNP
最も多くみられるのは「SNP(Single Nucleotide Polymorphism)(一塩基多型)」です。
SNPとは、塩基配列中の一塩基だけが違っているところのことで、約500〜1000塩基対に一つの割合で見られます。
一人あたり1000万か所ほどあると言われています。
 |
一般的な配列 |
 |
SNPの配列 |
この例では、左から三番目の塩基が違う文字になっていることがわかると思います。
DNAの塩基配列の違いですから、もちろん生物のからだに影響を与えます。
重要なタンパク質のコードが変化してしまい、病気にかかりやすくなることもありえます。
病気のかかりやすさは一つのSNPによって決められているわけではありません。
10個から20個ほどのSNPによって決められており、それぞれを「遺伝子素因」と呼ばれます。
遺伝子素因によっても影響度合いはまちまちで、危険因子を持っていても発症しない人もいます。
ゲノムにとっては一塩基の違いがタンパク質にとって重要な役割を果たしていることもありますし、特に生命にとってあまり重要ではないことも多々あるからです。
ここで重要となるのは遺伝子素因と周囲の環境の兼ね合いで、あくまで遺伝子素因はリスクでしかない、ということです。
よって、遺伝子検査で自分のリスクを知っておくことによって、病気の予防へと繋げることができるわけです。
マイクロサテライト多型
「マイクロサテライト」とは、2〜4塩基の配列を、数回から数十回繰り返している配列のことです。
この繰り返し回数は個人によって差があるため、「マイクロサテライト多型」というわけです。
同じ配列を繰り返すため、DNAのコピーミスが発生しやすくなり、それが変異として残って個人差に繋がる、というのが定説です。
だいたい3万〜10塩基対に一か所ほど見られ、一人あたり10万個ほど持っています。
科学捜査の場では、この違いのことを「STR」とも呼びます。
コラム
このような違いの影響が、目に見える形で出る場合もありますし、もちろんその逆もあります。
忘れてはいけないのが、DNAの変異を誰しもが持っているということです。
しかし、これでもヒトは個体間の差が少ない生物です。
ヒトとチンパンジーが分かれたのが約500万年前で、ヒトは比較的新しい生物だということに起因します。
多様性、という面においてはヒトはまだまだ未熟者なのでしょうか。
Design by