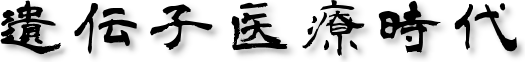転写
それでは、たんぱく質をつくるときに活躍するRNAについて詳しくみていきましょう。
まずは、RNAの一つ目の性質、「転写」についてみていきます。
転写とは、DNAの塩基配列をRNAにコピーすることをいいます。もう少し詳しく説明するならば、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、チミン(T)の4つの塩基がどのような順番で、どれだけの長さでつながっているのかを"正確に"コピーする過程が「転写」です。
DNAの鎖は2本でワンセットとなっていますが、転写の過程ではそのうちの一方だけが写し取られて、どちらの鎖がRNAにコピーされるのかはすでに決まっています。
遺伝情報として意味を持つ塩基配列がある鎖ではなく、その反対側、すなわち遺伝情報の鋳型となる方の鎖が転写されるのです。感覚としては遺伝情報のスタンプを作るようなものです。
それでは実際に次のDNA二本鎖が転写される場合を考えてみましょう。
 ←DNA鎖1:遺伝情報として意味を持つ塩基配列
←DNA鎖1:遺伝情報として意味を持つ塩基配列
 ←DNA鎖2:遺伝情報の鋳型となる塩基配列
←DNA鎖2:遺伝情報の鋳型となる塩基配列
これらの塩基配列から作られる伝令RNAがタンパク質の設計図としてきちんと働くためには、もちろん、伝令RNAはDNA鎖1と同じ塩基配列を持たなければなりません。
そこで、転写の際には遺伝情報の鋳型であるDNA鎖2の塩基配列が相補的にコピーされて、
 ←mRNA
←mRNA
と塩基が並ぶ伝令RNAがつくられます。
RNAではチミン(T)がウラシル(U)に置き換わるのでちょっとわかりづらいかもしれませんが、これはDNA鎖1の塩基配列と同じ並びを表していることがわかるはずです。
つまり、鋳型となる鎖を写し取ることで、遺伝情報として意味を持つ伝令RNAが作られたわけになります。
ちなみに、遺伝子の塩基配列を写し取った伝令RNAは、意味を持つRNAということで「センスRNA」とも呼ばれています。
Design by